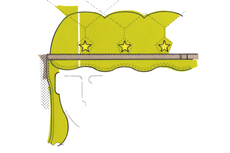新しい原子炉等規制法の第43条の3の23にその根拠条文があるが、ここには「(新安全基準に)適合しないと認めるとき」に、当該施設の使用停止や改造・修理などを命ずることができるとしか書かれていない。安全基準に適合するかしないかをどう審査するのか。適合するまでの猶予期間は認められるのか。申請書の内容は膨大になるが、審査はどの程度の期間をかけて、どのようなプロセスで行われるのか。こうしたことは、現時点で全く明らかではない。
本来、こうしたプロセスの具体化は、昨年規制委が立ち上がった後の第1の仕事たるべきだ。活断層の評価と比較すれば、法の執行手続きの整備に時間とマンパワーを割いてこなかった姿勢は大きな問題だ。規制委はアカデミックな学会発表の場ではなく、経済的資産として存在している原子力発電所の活用の可否を検討する場だからである。
効率性という視点
この最後の点にも関連するが、第2のポイントは規制の「効率性」である。福島第一原発の事故によって、いわゆる安全神話は崩れた。今後の原子力技術の利用に関する規制の課題は、リスクをゼロにすることを目的とするのではなく、リスク低減のために求める措置の強度やコストとリスクの低減度合いとの兼ね合いをどうバランスさせていくかにある。
米国の原子力規制委員会(NRC)は規制活動の5原則の1つに「効率性」を挙げる(他に、独立性、開放性、明瞭性、信頼性)。「納税者、電気料金を支払う消費者、認可取得事業者は皆、規制活動の管理運営は可能な限り最良の状態であることを求める権利があ」り、「規制活動は、それによって達成されるリスク低減の度合いに見合ったものであるべき」であり、「有効な選択肢が複数ある場合には、リソースの消費が最少になる選択肢を採るべき」だとする。
そうした原則に基づき、米国のバックフィット制度においては、NRCは「公衆の適切な防護を確保するための措置」に該当する場合のみ、コストを考慮せずに迅速なバックフィットを要求するが、そうでない場合には、NRCが改造・追加投資によるコストと安全性向上によるメリットを比較したうえで、実施の要否を判断することになっている。
日本においては、「ゼロリスクはありえない」ということを学んだにもかかわらず、むしろそれがゆえに、再稼働にむけてゼロリスクを要求する世論が強まるという逆説的な状況が続いてきた。規制委も、「グレーであれば安全側に立つ」といった表現で、そうした空気に寄り添うスタンスを取ってきた印象が強い。