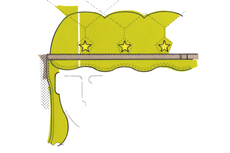ともすれば、規制委自身がゼロリスクの呪縛に囚われた規制活動を行っていないか、自ら顧みることが必要ではないだろうか。田中俊一委員長自身も、あるインタビューでこう言っている。「絶対安全とは言わない。言えばまた安全神話になる」(東洋経済オンライン)と。その立場を守ってもらいたい。
規制当局と事業者のあるべき関係
最後に「実効性」の問題だ。
これまでの規制行政については、福島第一原発の事故以降、さまざまな問題の指摘がなされてきた。特に、安全審査や検査が、安全基準への形式的な適合性を確認することに重点が置かれすぎ、全体の安全性を実効的に確保する活動に努力が振り向けられるようなインセンティブ設計がなされていなかったという点が最大の問題である。
10年ほど前に発覚した東京電力の自主点検記録に関する不正問題をきっかけに、品質保証計画に基づく保安活動が義務づけられることになった。これは、それまで安全性向上を事業者自らの責任で自律的に達成していくという意識がなく、国が策定する規制基準を遵守し、規制当局にお墨付きを得ればそれで十分という認識しかなかった原子力事業者の意識改革をもたらすものとなりえた制度改革だったのである。しかし、こうした検査型から監査型への移行は、手法の未成熟さや制度の理解不足などから、期待どおりの成果をもたらすことなく行き詰まっている。
米NRCは、スリーマイル島原発事故のあと適合検査を強化することで原子力安全の確保を進めようとした時期があったが、不適合が多発し稼働率が大きく低下、結局失敗したとの認識が広がった。そこで「We trust licensees, but verify them」(認可事業者は信頼する。しかしそれを検証する)を原則とし、現在に至っている。
検査の重点は規制の実施結果を見ることに置かれ、検査官は問題のある部分に集中することができるようになった。逆に原子力事業者の方も、規制当局に信頼されていることが前提であることから、自律的な責任感が醸成され、むしろ不適合は減少、稼働率も大幅に高まった。