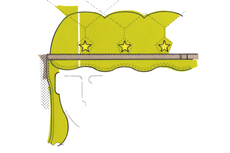ここでいう「信頼性」は広い概念である。規制のサブスタンスに加え、規制立案・実施のプロセスについての信頼性もある。規制のサブスタンスとは、主として現在検討されている新安全基準の内容のことを指すが、例えば話題の活断層の評価なども含む。こうした規制に関する規制委の判断や評価については、規制委に属する専門家のみならず、委員会外部(海外を含む)の専門家の間でも、その妥当性について大きな疑義が生じることがない程度まで、文書で明瞭な根拠が示されることが必要だ。
そして、規制のサブスタンスについての信頼度は、プロセスによっても左右される。活断層評価について言えば、過去の審査に携わった専門家は意図的に外し、4人(島崎邦彦委員長代理を除く)という少数かつ限られた分野の専門家だけで検討が行われている。むしろ、過去の審査メンバーを維持したまま、意見が異なる専門家を新たに招き、両者間で議論を闘わせることで信頼度が高まるとは考えなかったのだろうか。
さらに、調査検討の途中段階で各専門家が口頭で個人的な意見を開陳することは大きな混乱を招く。敦賀原発敷地内の破砕帯に関する評価が、その典型例だ。根拠を記した報告書案は1月28日に出されたが、それより前に、活断層だと最終的に認定されたかのように受け止められる会見が繰り返し行われた。
それに対し、日本原子力発電は、規制委に対して公開質問状を提示した(昨年12月11日)。事業者にこうした手段に訴えなければならないほど危機感を持たせた原因が評価作業の進め方にあるとすれば、規制委側は反省すべきである。規制委は自らの組織理念として「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める」(ウェブサイト)と掲げているからである。
また、「信頼性」には、法令に基づき文書をもって規制活動を行うことも含まれる。民主党政権の時代には、浜岡原発を総理の「要請」という圧力行政で停止させる。定期検査後の再稼働について法令根拠のないストレステストを課すなど、法治主義とはほど遠い原子力行政を進めてきた。
今後はこうした行政手法と決別し、規制委と政府、そして事業者がどのような権限と責任をもつのかを明確化する必要がある。さらに規制活動のプロセスも、規制委が行うそれぞれの行為の法的根拠を明確にし、その判断や指示を全てきちんと文書化していくことが重要だ。
その試金石が、今年7月に施行される予定の新安全基準によるバックフィット(最新の技術的知見を技術基準に取り入れて、既存の原子力発電所にも当該最新基準への適合を義務づけること)である。