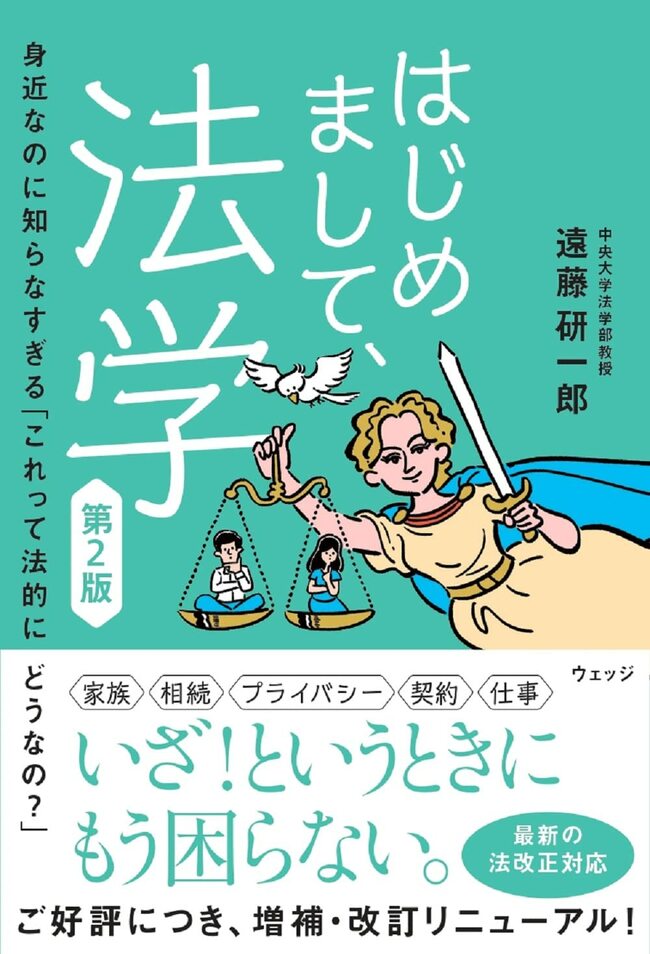「住む権利」を支える“居住福祉”的な発想
2015年9月、千葉県銚子市の県営住宅で、実の母親が、当時中学2年生の娘を絞殺するという事件が発生しました。報道番組などでも相当取り上げられていましたので、読者のみなさんの中にも、まだ記憶に残っている人が少なくないのではないでしょうか。
その母子は、困窮状態に追い込まれていました。母親の年収は、約100万円。国民健康保険料も未納状態でした。県営住宅の家賃は1万2800円でしたが、長期にわたって家賃を滞納したため、行政による部屋の明け渡しの強制執行が行われることになっていました。強制執行の当日、この殺人事件が起きたのです。
私には、この事件は、単なるやり切れない不幸な事件というよりは、今まで説明してきたような、日本の構造上の問題が大きく関係しているように思えます。
日本でも、分野次第では福祉が相当程度発達しているように思いますが、居住の領域は、驚くほど市場原理主義が支配しています。しかし、果たしてそれでよいのかは、慎重に考えなければなりません。
「住む権利」というものが、アイデンティティー、人格形成、人間的価値の形成に関わる憲法上の基本的人権として、国家が保障すべきであるという考え方があるのは注目に値します。居住福祉的な発想です。
たしかに、居住空間を失うリスクが誰にでも内在するものであり、かつ、居住空間の確保というものが、われわれが生きていくうえで必要不可欠なものであるとすれば、今まで以上に社会全体で支える仕組みを構築していくという発想も、十分にあり得る選択肢ではないでしょうか。