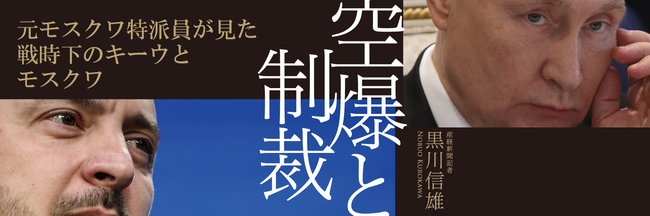ウクライナ戦争でロシアがすでに何十万人もの死傷者を出している一方で、NATOが30万人規模の部隊編成を可能としていることは、ロシアにとって深刻な脅威の一つと映っているであろう。
核シェアリングの強化と新たなミサイルの配備
核シェアリングはNATOの5カ国に米国が戦術核を配備し、一朝有事のときに当該戦術核の所在する国が米国大統領の許可を得た上で自国戦闘機に核を搭載し戦闘に投入されるという制度であるが、従来からその実効性には疑問が呈されていた。
例えば、核シェアリングの対象となっている5カ国(ドイツ、オランダ、ベルギー、イタリア、トルコ)はモスクワなど主要都市から非常に遠く、これらを標的にするには、現在彼らが保有する戦闘機(Tornado、F-16など)では航続距離が十分ではない。
しかし今日、上記5カ国は、トルコを除きいずれも戦闘機は十分な航続距離があってステルス性に優れたF-35Aに、また核爆弾はこれまでのB-61重力爆弾より命中精度の高いB61-12に替えるプロセスが進行中である。F-35Aの配備が完了する30年前後に向けて、核シェアリングはより実効性を伴うものとなり、欧州の戦略環境はロシアに不利に展開していくであろう。
艦隊の海洋行動における制約
ロシアは欧州方面に三つの艦隊(北洋艦隊、バルト艦隊、黒海艦隊)を有しているが、程度差はあるもののウクライナ侵攻の後、これらのいずれもそれ以前にはなかった制約に直面している。
黒海艦隊は、ウクライナによるドローン攻撃等で既に多大な損失を被っていることに加え、戦時における交戦国軍艦の通航を禁止するモントルー条約の規定により、ロシアの軍艦はボスポラス海峡の通航ができなくなっている。
バルト艦隊は、カリーニングラードに司令部をおき、サンクトペテルブルクにも艦艇を駐留させているが、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟により、ロシアはバルト海沿岸のほぼ全域を喪失し、同海はNATO諸国に包囲される形となった。
北洋艦隊はロシアの4大艦隊中最大で、対米抑止戦略の要であるが、NATOは14以降から、とりわけ22年以降、北洋艦隊がムルマンスクから大西洋に出る航行路に対する監視や海洋訓練を活発化させている。対潜哨戒機などによる監視活動が強化され、また対潜水艦戦や電子戦に対する訓練などが活発化しており、ロシア艦艇への監視強化と行動の制約が図られている。