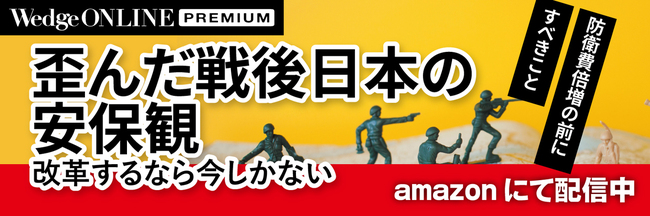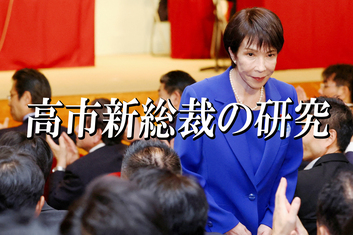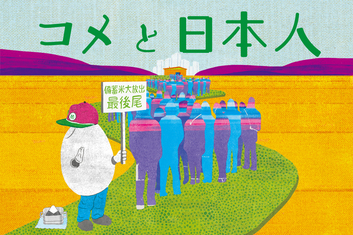国家と国家の関係のあるべき姿を、彼我の軍事的経済的力量の比較の結果に基づき評価し受け入れるべきだという冷厳な現状肯定方式の紛争処理は、第一次世界大戦以前の 19 世紀以前の勢力均衡による平和と安全確保の時代に逆戻りした感がある。
欧州諸国にとって、それはかつて自分たちの間に発達した秩序維持の規律であるからか、その道義的良し悪しを脇において、現実的な対応策として、各国共に各々の実力に応じて軍事力や経済力などを増強する過程を歩んでいる。一部には、核兵器による抑止力を欧州諸国に提供しようとすることも検討の視野に入っているとの報道もある。しかし、ほとんどのアジア諸国は、恐らく日本を唯一の例外として、そうした国家間の秩序維持の規律の中に主体的に身を置いた経験が乏しく、対処方法を見出し得ずにいる。
戦闘停止という課題だけに重点を置いている米国
無論、集団安全保障体制は、国連安全保障理事会の機能不全もあり、必ずしも完璧な制度には発達してきていない。とりわけ大国間の紛争については有効に機能する段階からは程遠い。
そんな中、紛争処理の基礎にある各国の領域主権の不可侵という法認識に関しては、諸国間に共通の基盤が成熟しつつある。しかしながら、今般、米国の新政権は、その法的基礎は度外視し、戦闘の停止という課題だけに重点を置いた紛争処理を主張しているように見える。