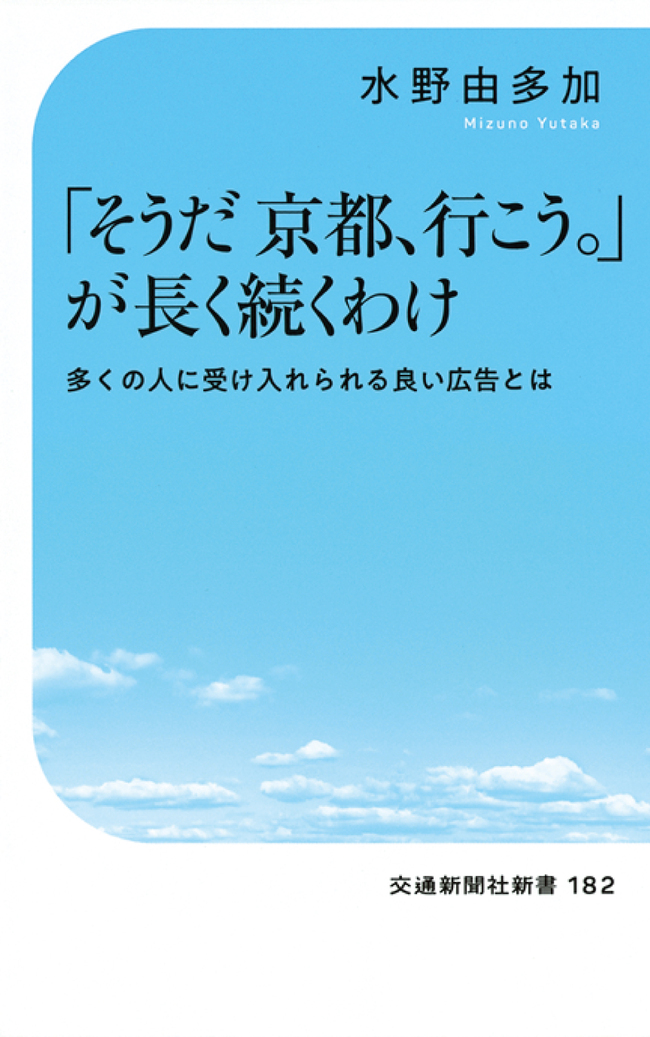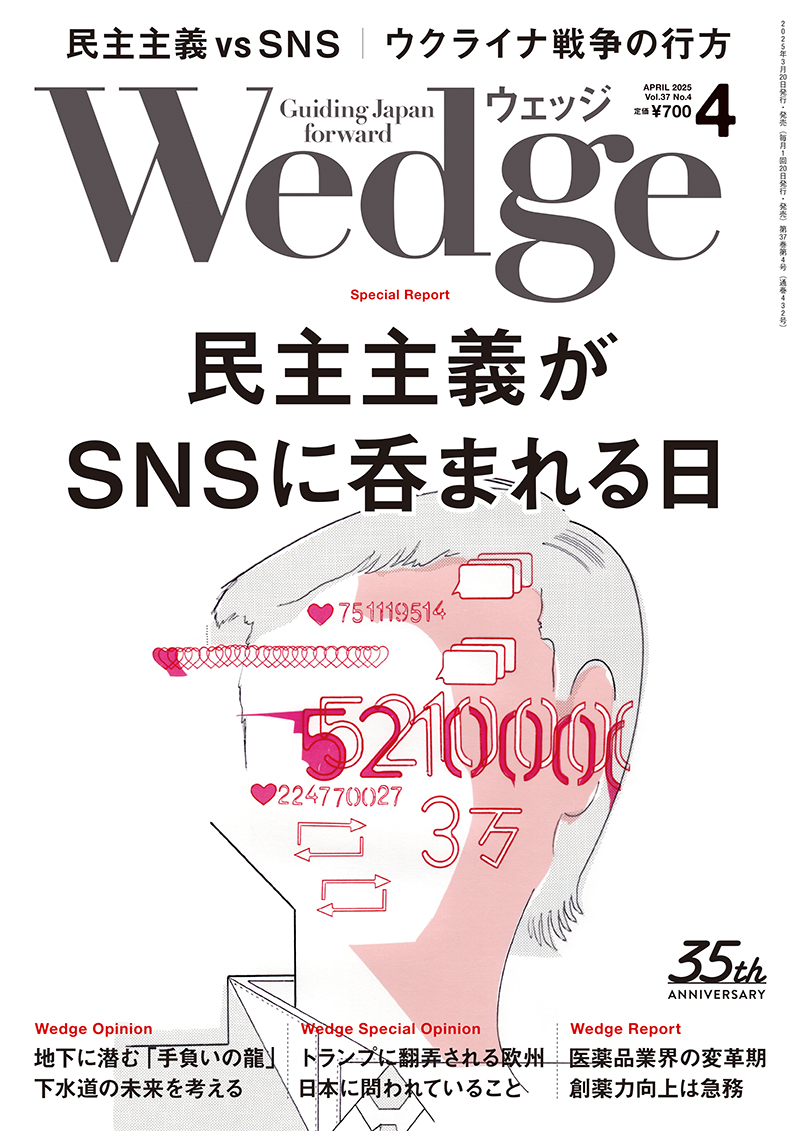科学と愛の物語
著者は東大で博士号を取得。専攻は地球惑星科学。専門的な話の中に人々の心の動きが編み込まれるこの5編の短編は、いずれも地方が舞台で、そこでの課題が舞台装置だ。「祈りの破片」では、住民の苦情から空き家を調査したところ、中から多数のレンガやコンクリートの破片が見つかる。これが長崎原爆の悲劇とつながり、ラストは涙なしにはいられない。「藍を継ぐ海」は、祖父と二人暮らしの中学生・沙月の物語。徳島県の南部で、アカウミガメがやってくる町に住む。沙月は夜、そのタマゴを5つほど盗んで自分で育てようと試みる。「藍」とは黒潮であり、遠く離れた人とカメをつなげていく。
依存症を語ろう
依存症の本質は必ずしも物質にあるわけではない──。麻薬を投与されたネズミが薬物依存症に陥った原因は、「麻薬」よりも檻に閉じ込められた「孤立」であるというラットパーク実験からみる回復の話や、大麻よりもアルコールの方が他害的行動に関係するという話からは、孤立やトラウマからの解消などが根本にあり、世間のイメージを変える必要があると思わされる。ニコチン依存症の精神科医・松本俊彦と、アルコール依存症の文学者・横道誠が赤裸々に語る往復書簡集。
愛される理由
この広告はなぜ、30年も変わらずに生き残ってきたのか、著者がこの歴史を「奇跡」と評価する理由は一体何であるのか、様々な側面から分析されていく。1993年から続くこの広告の「そうだ」の部分は、突然一人で旅に行くことができるようになった豊かな現代社会が長く表されると同時に、時代に合わせて変化する部分もある。短期的な販売促進を目的とせず、広告を通じて京都を表現し、京都とブランドを補強し合うことで長く愛されているという歴史は、学ぶ部分が多い。