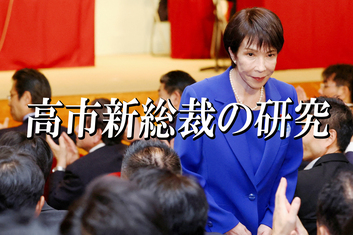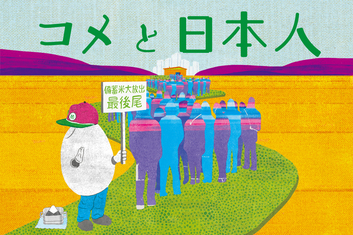貧しかったころ、篤志家がただで開放した図書を貪り読んで知識を得たカーネギーは、特に図書館に関する寄付に力を入れた。米国において1600以上、世界全体を合わせると2000以上もの図書館の建設を援助している。
「金持ちのまま死ぬのは恥である」とは彼の言葉で、家族に財産は残さなかった。フィランソロピーを貴ぶのがもう一つの米国の伝統である。
つまり貧困から身を起して成功するというセルフメイドマンの伝統と、成功した後フィランソロピーにまい進するという、アメリカの魂とでもいうべきものをすべて体現したのがカーネギーであった。
金銭ではなく、文化、心理的に受け入れられない
そのアメリカの魂を体現した人物が作った製鉄所が源流になっているのが今日のUSスチールである。USスチールは長らく世界一の鉄鋼会社であり続け、20世紀米国の発展を支えた。全米の鉄鋼生産高の3分の2を占めたこともあった。
その後、生産高は、1953年にピークに達したのち、日本などのアジアの国からの比較的安価な鋼鉄の輸出などによって低迷していった。しかし、多くの米国人の心には、米国が敵なしだったころの記憶と共にUSスチールは残っている。
その米国が世界一となる原動力となった企業を、よりによって、自分たちが開国させ、発展を助け、戦争直後には飢えからも救ったはずの「日本」の企業が、買収しようというのである。同業のクリーブランド・クリフス社の最高経営責任者(CEO)が、星条旗を掴みながら「アメリカだぞ。わきまえろ」と叫んだのが示唆的である。
日米首脳会談の直後、トランプ大統領が大統領専用機内で記者にUSスチールの問題について聞かれて、「ほかの会社ならいい、USスチールは心理的にだめだ」と答えているのが印象的である。この問題の根幹が、金銭的な問題ではなく文化的、心理的なものであることがこの発言に象徴的に表れている。
確かに日鉄の提案は、USスチールの経営者にも、労働者にも、ピッツバーグ市にも良い内容であったろう。老朽化しつつあるUSスチールの設備に日鉄が資金を投入し、最新技術も供与して、よい鋼鉄を大量に生産できるようにすることは米国産業界全体にとっても良いことであるのは間違いない。しかし、この場合はそろばん勘定で済む問題ではなかった。日鉄の提案は、相手国の文化背景や歴史を顧みない、多くの米国人の気持ちを無視したものではなかったのか。
USスチールを守り投資を得る結末か
さて、今回の再審査で対米外国投資委員会(CFIUS)はどのような結論を出すだろうか。トランプ大統領がわざわざ再審査を要請したことから前回同様ということはないだろう。
トランプは、再審査要請の2日後、「日本に渡るのは見たくない。とても特別な会社だ」と念押しした。再審査要請によって審査結果を変えるように求める一方で、子会社化までは認めるなというトランプ大統領からのメッセージではないだろか。この見方が正しいなら、100%完全子会社化という日鉄の当初案が通るのは難しいだろう。
おそらく、過半を切る株式取得であれば安全保障上の問題はないというところに落ち着くのではないだろうか。バイデン大統領が全くのゼロ回答によって米国の鉄鋼会社を「守った」ものの、それだけだったのに対し、トランプ大統領はUSスチールを守っただけでなく、巨額の投資も引き出して凄い大統領だ、という形になるのだろうか。