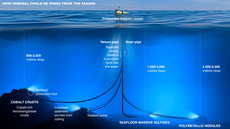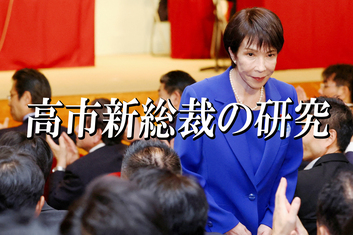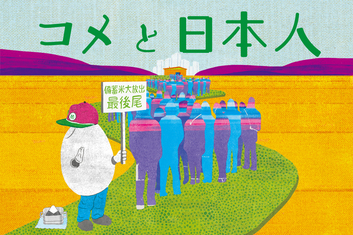訴訟の社会的意義は何か
今回の訴訟は、民法709条に基づく「不法行為による損害賠償請求」だ。ある企業の商品が危険でもないのに、極めて危険な薬剤であるかのように拡散・喧伝されることによって、その会社の信用と商品が大きく毀損されたというのが訴訟の理由だ。間違った情報が流れているのに、そのまま黙認すれば、会社がその危険性を知りながら隠して販売しているとも受け取められかねず、見過ごすわけにはいかないのだという。
今回の訴訟の代理人を引き受けた清水陽平弁護士(法律事務所アルシエン)はネット上の誹謗中傷の削除を求めたり、虚偽情報の法的責任を追及したりする分野に強い弁護士だ。今回の訴訟を通して、「情報発信(投稿)の前に自分の知識や持っている情報の正しさを検討・検証することの重要性に気付くきっかけとなって欲しい」と話し、今回の訴訟には、安易な虚偽情報の投稿が横行するインターネット空間で情報発信の自己点検を促す社会的意義があると強調する。
言論の自由と誹謗中傷は別
グリホサートなど農薬に関する情報の真偽をファクトチェックしているウェブサイトとして、「AGRI FACT」(アグリファクト、農業技術通信社運営)がある。そのサイトでグリホサートの科学的なリスクを解説する動画などに登場する唐木英明・東京大学名誉教授(薬理学とリスク論が専門)は今回の訴訟に対して次のようにコメントしている。
「風評に悩まされる企業は、反論するとかえって炎上するとして、風が収まるまでじっと耐えてきた。このような新聞・テレビ時代の常識は、SNS時代の現在には通用しない。刺激的なフェイクニュースを流して収入を得るネットビジネスが広まり、風評は急速に拡散してしまうからだ。その対策として、悪質な拡散者を提訴することは極めて有効であり、多くの企業が裁判の行方を注目しているだろう。よくある言論の自由という言い訳を、司法が明確に否定してほしい」
言論の自由には誹謗中傷する自由までは含まれないはずだが、グリホサート問題に似た誹謗中傷は遺伝子組み換え作物やゲノム編集食品、放射線を活用したコメの新品種にもみられる。今は、誰でも匿名でいとも簡単に真偽不明の情報を投稿できる時代になった。今回の訴訟が安易な投稿者にどこまで自己チェックを促す機会につながるのか大きな注目を集めそうだ。