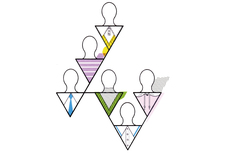年々世界情勢が目まぐるしく思える中、中国を取り巻く昨年の動きも本当に多岐にわたった。中国の国際的存在感は確かに高まったが、中共の一党支配のもとで蓄積された矛盾が、ここに来てますます同時多発的に深刻化しているのも確かである。そんな中国は、果たして今後どうなるのか。日本としては、従来にも増して中国の意図を正確に見極めて適切に対応する必要があろう。
しかし筆者が思うに、このような状況にもかかわらず、多くのメディアや国内世論が中国の現状を形容する際に、些か冷静さを欠いてはいまいか。もちろんその理由として、ここ数年来日本が中国から蒙ったハラスメントの反動ということはあろう。あるいは中国がリーマン・ショック以来、世界各国の大型インフラ投資に激しく食い込み、日中両国が角逐する場面が増えているためであろう(ひとつの象徴的事例はインドネシア新幹線をめぐる問題であろうか)。
とはいえ日本も、バブルが崩壊したからといって日本社会全体が消えてなくなったわけではなく、長らくの低迷を経て再浮上が図られてきた。これと同様に中国も、たとえ多くの現代日本人から見て途方もない問題を抱えているとしても、中国社会の基本的なあり方や国際的なイメージが致命的にダメージを蒙っているわけではない。むしろ、30〜40年前には片鱗すらなかった大量消費社会は確実に根付いている。ついこの間まで世界最貧国並みであった国が、課題山積ながらも経済力を上げたこと自体の重みは無視できない。
そして、経済は減速しつつもそれなりに活力がある中国だからこそ、国際社会は様々な「期待」を中国に向けていることは過小評価できない。例えば英国やドイツはその代表例であろうが、中国との距離が極めて遠ければ、安全保障上の脅威として中国を見なす必要がなく、単純に経済的利害に基づいて中国との関係を重視するのであろう (もちろんそれは、各国の国内世論が一様に中国との関係強化を歓迎していることを意味しない)。
ゆえに、そんな世界の動向を睨む中共が考える次の一手も、日中関係が基準ではありえない。生々しい弱肉強食外交そのものと言ってしまえばそれまでだが、中国はかりに某国(例えば日本)との関係が悪くとも、他の国との関係で利益を得られるならば、ますます某国との外交戦に打って出て妥協を勝ち取り、あるいは完全に力を削ぐことで、自国の利益を一方的に増やせば良いと考えている(毛沢東流の「敵と我の矛盾」論は今も生きている。敵は、中共に勝ち目がなければ完膚なきまで打倒するべきであるし、あるいは勝ち目がなくとも想定外の強い態度を見せて相手を怯ませるという方法もある。その具体的な一例は、「第二次大戦後の世界秩序を守らない日本」という、昨年も中国の国連大使が繰り返した根拠なき非難であろうか)。
中華民族の偉大な復興
 iStock
iStock
そもそも、中ソ関係が極限的に悪ければ、当面の生き残り策として日米に接近したものの、ソ連が崩壊し中国が発展すれば対日米妥協の必要もない。そこで、長期にわたり「韜光養晦(能ある鷹は爪を隠す)」の態度で先進国から資金と技術を獲得し、やがて「中国夢」の名において西太平洋における日米の存在感を削ごうとしてきた。
これこそが、中共の言うところの「世界民族の林の中で屹立する」「多極化した世界の中で成功者の位置を勝ち取る」行為であり、「中華民族の偉大な復興」の姿である。
このような世界観に即して言えば、中共のいう平和は、あくまで中共の立場に理解を示した外国との、二国間関係の積み重ねとして成立する。中共が既存の(したがって中共にとって外在的な)国際秩序の模範的な一員に生まれ変わることによって実現するものではない。一見すると「平和的崛起・台頭」というスローガンとともに進められてきた「新思考」外交にしても、後発組として国際秩序に参入して成功を収めた中国が、中国の台頭という国際秩序の新しい現実にふさわしいように、既存の秩序を改変するのを当然のものとみなす(しかも、その代表的論者として知られる時殷弘氏の議論の端々に現れているのは、「本来中国が国際社会において得るべき座を占め続ける」米国への激しい敵意である。彼らからは「対日新思考」と称して日本との接近が語られたこともあったが、それはあくまで日米を離間させるためであった)。