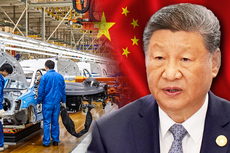EU圏内では、人々は自由に移動し、仕事をします。その時に、英語はTOFELでは〇〇点で、TOEICで〇〇点、ドイツ語はOSDで〇〇点……と別々の評価基準で言われてもわかりづらいですよね。そこで、どのように言語を教え、どう評価するかを40年近くにわたり言語教育の専門家が研究しCEFRを作り上げました。CEFRでは、Can Do statements と呼ばれる能力記述文を使い、どんな言語であっても共通の尺度で言語能力を表せるのが画期的です。その他にも、言語は生涯をかけて学ぶものである、その為には学習者の自律性を涵養すること、理想的なネイテイブスピーカーを目指す必要はない、などの言語教育理念に立脚していて、世界中の外国語教育に大きな影響を与えています。
しかし、文科省は、複言語主義の思想やCEFRの全体像を理解せずに一部だけを導入し、「到達目標」として使ったため、日本では本来の「評価の枠組」を表す言葉ではなくなってしまいました。
――次期学習指導要領にも記載されているんですか?
鳥飼:中央教育審議会の答申では、CAN-DOという言葉や、CEFRについての説明が入っていましたが、2021年施行の中学校の学習指導要領では、どちらの用語も消えました。ただ、「〜できるようにする」という表現は残っています。
――ところで、英語教育の主軸が昔は文法や訳読などが重視され、1990年代からはコミュニケーション重視になったと。おそらくより実践的なものへと変更しているとは思うのですが、鳥飼先生がご専門の異文化コミュニケーション論の立場から、現在の英語教育についてどうお考えですか?
鳥飼:学習指導要領に関しては、「コミュニケーションを目指す」としていながら、言語力育成しか言及していません。言語力を身に着けたとしても、それをどうコミュニケーションに結びつけるかについてはまったく触れられていない。言語知識だけでは、コミュニケーションは成立しないのです。
他にも小学校の学習指導要領を読めば、言語の専門家でなくても驚くような高度な授業内容が書かれています。そもそも小学校には英語の専門教員がいないのですから、指導できるわけがありません。これについては、文科省もなんとかしようと、英語ができる(とされる)学外の人材に与える「特別免許」や、小学校教員を対象にした短期の「特別研修」を各大学に依頼するなどで対応しようとしていますが、泥縄式の印象です。本来は免許法を改正して、小学生に英語を教える免許を新たに作るべきです。そのあたりを含め、英語の学習指導要領の問題については新書を執筆中です。
――最近の一番の話題は、小学校での英語の教科化です。
鳥飼:日本の英語教育について、私の予想では、このまま生徒たちの英語力は伸びないままだと思います。小学校の英語教育は2020年から5,6年生で教科として教えられ、3,4年生から外国語(英語)活動が始まりますが、「開始時期を早めても英語を話せるようにならないじゃないか」と結局はゆり戻しが起き、ゆとり教育と同じような末路をたどるのではないかとさえ思います。
ただ、子どもたちにとっては、小学生は一度しかありませんから、現状のような英語教育を受けないとならないのは不幸でしかありません。
小学校での英語の教科化に関しては、政府の教育再生実行会議で決定していましたから、政治主導で進められた方針に文科省も従うしかないでしょう。