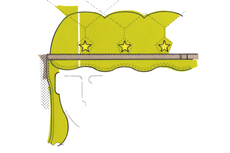激しい上層部批判や世代間断絶は、しかし別の見方をすれば「大正デモクラシー」の延長線上にあった。筒井清忠氏(帝京大学教授)の言葉を借りれば「彼らもまた大正デモクラシーという一つの時代の子」であった。
戦後秩序の構造的欠陥に直面した日本
「大正デモクラシー」を外から支えた国際体制も限界を露呈した。国際連盟は大きな期待をもって創設された。その歴史的意義は過小評価されるべきではない。しかし米国が議会の反対から不参加となるなど、集団安全保障機構としての実効性に欠けたことは否めない。
太平洋と極東における現状維持と平和共存を約した「ワシントン体制」は、そうした国際連盟の不十分さを補完する性格を持っていた。
しかし、しばしば指摘されるように、ワシントン体制もまた構造的欠陥を抱えていた。第一に、この体制が中国における列強の既得権益を黙認することで成立していたことである。中国が政治的に弱小で、その国民が権益の収奪に無関心なうちは良かった。しかし強力な中国中央政府が成立し、国民のナショナリズムが勃興したときに、中国が奪われた権益の回収に乗り出すことは自明であった。そのとき日本は日露戦争の血の犠牲で贖った満州権益を放棄できるであろうか。
第二に、この体制はソ連の存在を無視することで成立していた。これは特に日本にとって大きな問題であった。ロシア(ソ連)は日本にとって宿命の仮想敵国であり、その想定戦場は満州である。ソ連が未だ弱体なうちは、日本はソ連の脅威を軽視しえたし、想定戦場である満州の問題でも寛容でいられた。しかしソ連が無視しえないほど強力となったとき、日本は満州を物理的に抑えたいという軍事的誘惑から逃れられるだろうか。
第三に、この体制は自由で開かれた経済活動によって世界は等しく発展できるという楽観的な未来予測に基づくものであった。しかし度重なる不況によって日本経済が疲弊し、国際的には世界恐慌に端を発するブロック経済体制が推進されるとき、日本は楽観的な未来予測に信拠し続けることができるだろうか。
第四に、極東問題に関する日本と欧米列強との非対称性である。欧米列強にとって極東問題は基本的には経済問題であり、国家の生存や尊厳に関わる問題ではない。しかし日本にとって極東問題は国防問題であり、満州は「建国神話」(日露戦争)の聖地でもある。経済的意味に限っても欧米列強にとってのそれとは重要性が違った。このことが危機発生時の両陣営の相互理解を困難にした。
第五に、ワシントン体制は平和維持のための諸国間の約束であり、その約束を遵守させるための実行手段を伴っていたわけではない。平和維持の実行組織は国際連盟である。しかし国際連盟の集団安全保障機構としての実効性は疑わしい。ではワシントン体制が綻びようとしたとき、誰がそれを守護するのか。
こうした構造的問題点が端的に露呈した事件が中ソ紛争(1929年)であった。この紛争は、中ソ共同経営であった満州の東支(中東)鉄道を中国が実力回収し、これに対してソ連が武力介入して権益を奪還した事件である。
中ソ紛争は国際連盟・ワシントン体制の前提となってきた国際情勢が今や明確に変わりつつあることを示した。中国の権益回収の過激性と切迫性、そしてソ連の軍事的強大化である。さらに紛争に際して国際連盟もワシントン体制も無力を露呈し、最終的に問題を解決したのが軍事力であったという厳然たる事実である。