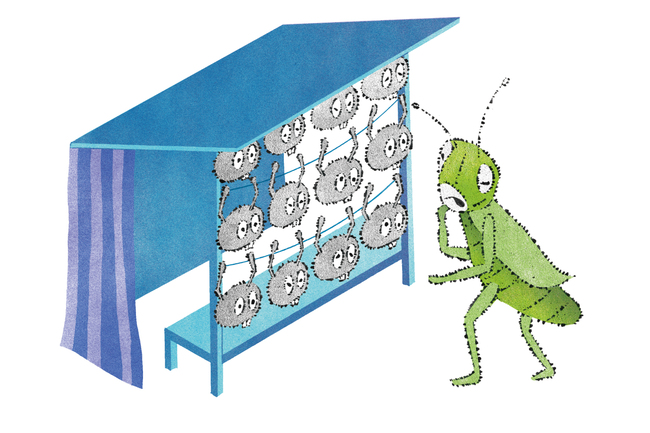50代半ば以上の世代は、日本経済を支える優秀な官僚制が海外から称賛された時期を覚えているだろう。米国政治学者チャルマーズ・ジョンソンの『通産省と日本の奇跡』(1982年、勁草書房)などで、戦後の経済成長や社会の安定に果たした官僚の多大な役割が指摘された。拡大するパイの配分をめぐって、各省は族議員と組んで活発な政策競争を続け、国内でも「官僚は鼻もちならないが政治家に比べて清廉で有能」という評価が定着していた。
こうした評価は1990年代に一変する。少子高齢化から生ずる財政負担がバブル経済崩壊で顕在化し、冷戦終結から急激なグローバル化が進んだことで、従来の縦割りとボトムアップの限界が露呈した。行政の立ち遅れが目立つ中、主要省からは機動性向上に向けて人事の自由化を求める声が上がる。
一方、同時期に、文部・労働両事務次官の逮捕(リクルート事件)、大蔵省過剰接待、厚生・防衛両事務次官の逮捕など、幹部官僚の腐敗が相次いで発覚した結果、「政策失敗の原因は官僚の省益追求なので、選挙で選ばれる首相が厳しく統制すべき」という集権化が支持を集めるようになる。
ただ、期待が大きかった反動か、メディアや国会からの官僚バッシングは激しさを増し、議論は原因分析を超えた懲罰的な色彩も帯びていく。
組合からの訴えにより、働く側を置き去りにした改革を危惧した国際労働機関(ILO)からは、公務員の労働基本権制約への見直し検討や組合との協議などを要請する意見書が届いた。
さまざまな要求が混在する中、2008年、与党(自民・公明)と民主党(当時)との合意を経て、5年以内をめどに実現すべき改革パッケージを列挙した国家公務員制度改革基本法(以下、基本法)が成立した。そこでは「幹部人事一元管理の導入」「事務を司る内閣人事局の創設」と並んで、「政官関係の透明化」「人事に関する内閣官房長官の国民への説明責任」「多様な人材登用、官民人事交流促進」「協約締結権の付与」など多岐にわたる項目が列挙された。