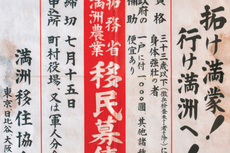塩ほど大切な調味料はありません。食材の味を引き立ててくれるからです。その中でも「これは!」と驚いて、今では、丸の内、日本橋浜町、池袋で運営するカフェ・レストランの全店舗で使っているのが百姓庵の「海の塩」です。これほど野菜の甘味を引き出してくれる塩はない。そう力説すると、担当編集者から「確かに産地などによって味は違うけど、百姓庵の塩が特に優れているのはなぜ?」と問われ、「海水が綺麗だから」と思っていたのですが、本当に正しいのか知るべく、百姓庵の代表で塩匠の井上雄然さんの元を訪ねました。
山口県長門市の中心部から、陸繋島である油谷島まで自動車で向かいます。海は目の前なのですが、山の中を走ることになります。まさに海と山がつながっている印象です。百姓庵の塩工房に着くと、海に向かって竹で組まれた櫓が立っています。その先にはエメラルドグリーンに輝く海が見えます。大袈裟ではなく沖縄のような南国の海の色に見えます。早速、井上さんが櫓の仕組みを教えてくれました。
「これは立体式塩田と呼びます。海水を汲み上げて竹に流します。表面積が大きいので、太陽光や風によって水分が蒸発するので短い時間で海水を濃縮することができるのです」
百姓庵の塩の美味しさの秘密を聞くと、意外な答えが返ってきました。
「海水が綺麗なことはもちろんですが、それだけではありません。レストランのシェフなどには驚かれるのですが、ここの海水はそのまま飲むことができるんです」と、井上さんは海岸に案内してくれました。手でひとすくいして海水を飲んでみました。一般的に、海水浴などで海水を飲み込んでしまうと塩辛く、むせてしまうのが普通ですが、ここではそうならず、確かに飲むことができます。
「この油谷湾には2つの大きな川があって、山からの栄養分が注がれています。淡水が入るので塩分濃度は高くないのですが、栄養素が豊富で海藻や植物性プランクトンがたくさん育つのです。塩づくりを志した時、それこそ全国の海を回ってみたんです。なかなか良い場所がないと思っていたら地元(下関)から近いこの場所を発見したのです。まさに灯台下暗しでした」
これが百姓庵の塩の美味しさの秘密なのです。さらに驚きなのが季節によって塩の味が変わるということです。
「例えば、夏場の塩は味が濃くなります。それは梅雨があってより多く山からの栄養分が海に注がれるからです」
釜焚室にも案内してもらいました。ここで濃縮した海水を薪で焚くのです。中に入ると薪の香り、そして80度の暑さと猛烈な湿気です。塩分を含んだ蒸気はどこか心地よく、「サウナマニア」の私にはたまらない空間でした。最後に、「百姓庵の塩に最も合う料理はなんですか?」と、井上さんに尋ねると「おむすび」とのことでした。
塩に関する本は、ほとんど読んだという「塩マニア」の井上さんからは、「フランス革命と塩」「インドのガンジーによる塩の行進」など塩に関するエピソードが次々に出てきました。私も興味を持って、同じ山口県出身の宮本常一の『塩の道』(講談社学術文庫)を読んでみました。製塩方法、塩の交易。そして、オオカミが日本にいた当時、夜に塩を運んではいけなかったことなど、面白いことばかりです。どこにでもある塩ですが、だからこそ毎日人が必要とするもので、いざなくなると、命にも関わるのです。
百姓庵の塩は、山口県内の道の駅などの他、「百姓庵オンラインショップ」でも購入することができます。
山口県長門市向津具下1098-1 0837-34-0377