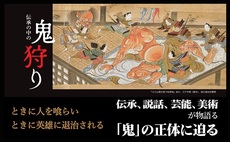それは、貿易の議論から除外されてきた者に手を差し伸べ、単に議論に招くだけでなくその声を取り入れて、新しいグローバル経済で繁栄できるようにすることだ。また、デジタル貿易ルールの検討でも人々を中心に据えている。
米国企業は強力で、革新的で、ダイナミックだ。公平な競争環境が整えば、競争し、繁栄することができる。
しかし、中国は、単なる貿易相手国ではなく、主要な経済分野で世界支配を追求している国だ。バイデンは、中国の不公正慣行、特にサイバー窃盗に対抗するために最近、電気自動車(EV)や電池等一連の商品に対する関税引き上げを指示した。
これらの関税は、米国の労働者と企業、そしてわれわれの投資を守るものだ。他の国も中国の非市場的な過剰生産への懸念を深めている。
われわれは世界をより安全で公平な場所にしなければならない。そして、それはわれわれが共に行うべきものだ。
* * *
関税ですべてを解決できない
タイ通商代表のドクトリンには強い違和感を覚える。彼女のナショナリスティックなレトリックは、「貿易政策は、過去40年間トリクルダウンのアプローチを踏襲してきた。しかし、市場に委ねることが国内経済政策の労働者への利益をもたらすことに限界があることを認識するなら、貿易に関しても同様に限界があると認めねばならない」、「貿易政策が民主的な責任から分離されたまま、地域社会は壊滅的な影響を受けてきた」との主張に凝縮されている。
タイの議論で特に引っかかるのは、①議論がスタティックで、問題を成長や輸出拡大等ダイナミックなプロセスとして見ていないこと(ゼロ・サムのパイの取り合い思考になっている)、②政府や政治の介入と補助金を過大に重視していること(広範な介入では社会主義国家と同じになる)、③ミクロとマクロの均衡を欠くこと、④全体的な理想論が欠落していること(公共政策には行先の理想像や思考が不可欠だ。消費者や生産者の視点も重視すべき)等である。
タイは労働者の「声を取り入れ」ようとする。しかし、時として部分的利益を超えて全体的利益や、短期的利益ではなく長期的利益を確保するために関係者を説得することも民主主義の下では必要となる。現に、日本製鉄のUSスチール買収案は労働組合の反対により正論が阻まれている。