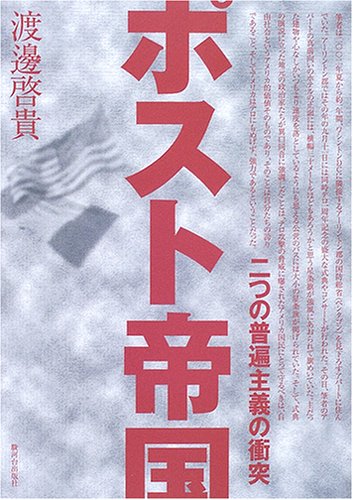同委員長は再選後の最初の訪問地をインドにすると発表、その大きな目的はトランプ政権の政策に備えた貿易問題への討議だ。中国とも協力関係を深化させている。1月中旬にはメキシコと自由貿易協定(FTA)を発表したが、すでに2024年12月にメルコスール(アルゼンチン・ブラジル・パラグアイ・ウルグアイ)との自由貿易協定を結び、カナダとのEU・カナダ包括的経済貿易協定(CETA)の深化を考えていると伝えられる。
世界は第一次トランプ政権時代にその手法を学び、それぞれの形で備えをしているかのようだ。カナダのトルドー首相は「対抗策の準備はできている」と事前に語っていたが、トランプの関税引き上げ措置の直後に早々に報復関税を発表し、同時にトランプの要望に応えた。ディールに応じたので、トランプはひと月高関税実施を延期した。メキシコに対しても同様だった。暫定的だが、ここまでは一応合意のプロセスだ。
EUも報復関税を含むいろんな手段を準備しているようだ。フォンデアライエン委員長は2月には、対外経済政策の大きな修正計画を発表する予定であると述べたが、資本市場の統一を目的として、投資向け口座に数百万ユーロを導入する計画である。トランプ政権の高関税政策に対抗して、EUは開放政策をとること、米国から離れて貿易関係をさらに多様化することが目的だ。
トランプ政権がメキシコへの高率関税政策に備えて、EUはラテンアメリカ諸国と貿易関係を強化する構えだ。トランプが高い率の引き上げを宣言したので、それも緊急のテーマになる。その一方で中国の不公正な貿易を承知の上で、ヨーロッパは建設的な中国との関係を通して実利をとる方向も模索する。
「イラク攻撃」論争での「対米包囲網」のデジャヴュ
つまりフォンデアライエン委員長の主張するプラグマティズムの手法とは、ユニラテラリズムに対するマルチラテラリズムによる対抗策と、解決のための妥協・合意なのである。
筆者は20年ほど前に、21世紀前半は米国のユニラテラリズムと欧州そのほかによるマルチラテラリズムの対抗構図が続くのではないかと、イラク戦争をテーマとした拙書(『ポスト帝国――二つの普遍主義の衝突』(駿河台出版、2006年)、『米欧同盟の協調と対立』(有斐閣、2008年))で主張したことがある。冷戦終結をアメリカの勝利、アメリカ時代と考えたブッシュJR大統領からトランプ第二次政権まで冷戦後のアメリカ外交はこの二つの軸を揺れ続けていると思う。
筆者はトランプ政権再来に際して、形とテーマは違うが、「デジャヴュ」の感覚を禁じ得ない。イラク戦争開戦前後の02年夏から翌年秋まで1年余筆者はワシントンDCにいて、経緯をつぶさに観察した。ブルッキングス研究所や戦略国際問題研究所(CSIS)など多くのシンクタンクを週に何度も訪れ、ホワイトハウスでも意見交換した。
帰国後、先の2冊の本を出版したが、その大きなテーマはふたつの方向性は今世紀半ば近くまでは続くのではないか、という見通しにあった。イラク戦争間近というような切羽詰まった状況とは異なるが、米国外交手段の在り方とそれへの欧州による対応の仕方の構図は依然として変わっていない。
このときイラク攻撃を強硬に主張するブッシュ米国に対して国連安保理で「開戦は時期尚早」と反対したのは独仏両国だった。そのときに論議に上ったのは米国の「ユニラテラリズム」に対抗する「マルチラテラリズム」という対立図式だった。
そしてその他の多くの諸国を巻き込んだマルチラテラリズムの手法による「米国包囲網」の形成だった。結果的に米国は国連安保理でのイラク攻撃決議をあきらめ、有志連合による単独攻撃に出て、イラクの混乱をかえって助長した。
そこからアメリカは学んだのか。それともますます迷走し始めたのか。もしトランプの単独主義と本来はそれには矛盾する「ディール」をセットとして考えると、それはトランプ流の妥協手法と言えなくもない。もしそうだとすると、ブッシュ大統領後のオバマ大統領はマルチ外交とオフ・ショアポリシー(時宜的介入主義)で単独主義から後退、そしてトランプのディール外交は米国流の対外交渉手段の変容、発展ともいえる。