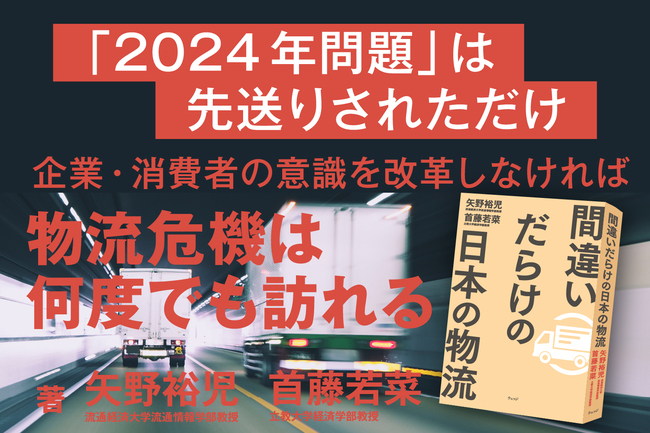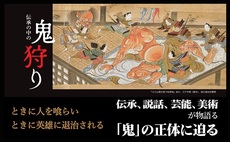そこで同社は、この3年で有給休暇の取得率を100%にし、労働環境の改善に取り組んできた。また、労働時間は削減しても、賃金は下げてはいない。給与を下げるとドライバーのモチベーションが下がり、離職につながってしまうためだ。厳しい経営状況にあるが、「ドライバーは、会社にとって必要不可欠な宝物。最後まで守る義務がある。賃金は上げても決して下げない」。
過重な附帯業務を伴う運送からの撤退
同様に、「2024年問題」を契機に、これまで引き受けてきた附帯業務を見直した事例は数多く存在する。
ある中小の運送会社は、長年にわたり2次請けでセメントを運んできた。160キロメートルほどの距離を走り、地元の大手企業に耐火セメント12トンを配送する仕事だ。
帰り荷の積み込みを終えて帰社するのは夕方になるが、そこで仕事が終わるわけではない。翌朝8時半、ドライバーは補助員1人を連れて、再度、着荷主のもとに向かう。フレコンパックに入ったセメントを荷主先のフォークリフトを使って、約300メートル先の工場裏のホッパーへ運び入れなければならない。それが終わると、次は2階にあるホッパーにリフトを使ってセメントを持ち上げ、それをローラーに乗せ、奥まで押し込む作業を行う。最後にセメントが入っていた袋をすべて回収し、自社で製作した空袋回収ラックに押し込んで持ち帰る。加えてローラー横に置かれたパレットも回収し、次の輸送時まで保管し、次回の引き取り時に持っていく。これら2人がかりで行われる附帯業務を、無償で長年担ってきた。
こうした附帯業務は、その負担があまりに大きいという問題のほかに、他社のフォークリフトを操作することの問題もある。ドライバーにとっては、不慣れな車両の操作を求められ、整備不良の車両を操作しなければならない場合もあるし、保険に未加入のまま車両を操作しなければならない場合もある。
ある日、いつも通り作業をしていたところ、2階にセメントを運び入れる際、フォークリフトのマストが、建物の屋根樋にぶつかり、樋を破損させてしまった。その後、荷主から元請け業者を通じて、9万円の修理代の請求書が送られてきた。
「最初はね、もちろん代金を支払うつもりだったんですよ」
しかし同社の社長は、はたと考えたという。「なぜ、ここまでの作業をしながら、破袋、破損に関してこちらがすべて持たなければならないのか」と。そう考え始めると、これまで我慢してきたものが一気にこみあげてきた。長い間、繰り返し附帯作業費の支払いを求めてきた。運賃の値上げも交渉してきた。しかし、それらが受け入れられることはなかった。