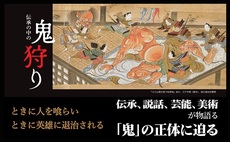働き方改革によるトラックドライバーの残業規制により、「物が運べなくなる」として大問題となった「物流2024年問題」。しかし2024年4月を迎えたとき、「物が運べなくなる」ことはなかった。
では、2025年を迎えた今、問題は解決されたのか? 騒ぎは杞憂だったのか? 答えは否だ。表面上の対策は打たれたものの、根本の業界構造は何も変わらず、物流現場は限界を迎える日は、刻一刻と迫っている。
本連載では、「2024年問題」を経た物流の現場を歩き、何が変わり、何が変わらなかったのかを分析する。
*本記事は『間違いだらけの日本の物流』(共著、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
物流「2024年問題」のきっかけとなった改正労働基準法の施行、および労働時間ではなくトラックドライバーの拘束時間を規制する「改善基準告示」の改正の施行。これらの事態を受けて、一部の中小運送会社では、拘束時間が長くならざるを得ない仕事から撤退する動きも見られた。
長距離輸送からの撤退
東北地方に位置するある運送会社は、改善基準告示を守るために、一部の仕事を断ることにした。
同社は、地場輸送のほかに、中距離輸送と長距離輸送を長年手がけてきた。しかし2024年4月を迎えるにあたり、長距離の仕事をすべて取り止めた。
「拘束時間を守りながら輸送を続けようとすれば、中継輸送をしないといけない。でも、うちぐらいの規模だと、新たな営業所を作るのは大変だし、他の会社と一緒にやろうなんてすれば、運賃をもっと高くしないといけない。どう考えても無理でしょ。早々にあきらめました」
むろん「あきらめる」前に、荷主に運賃の値上げ交渉を行った。だが、もっと安く運ぶ会社もあると言われ、受け入れてもらえなかった。実際にその荷物は、以前の運賃水準で他社が運び続けている。その会社が改善基準告示を遵守しているのかは分からない。
加えて、同社では、それまでおよそ4割を占めていた下請けの仕事を1割まで減らした。ここ5年ほどは軽油代も車両整備費も上昇してきたが、下請けの運賃はなかなか上がらなかった。元請け業者にコストが増加していると相談しても、「もっと安く運んでいる事業者もいる」「だったらお宅に頼まない」と言われ続けてきた。
他方で、荷主と直接顔を合わせて交渉している仕事では、自社の切実な実情を伝えることができ、運賃値上げに協力してもらえる場合が多い。下請けの手数料を引かれることもない。「2024年問題」を契機に、改善基準告示が遵守できないような運送からは手を引くことを決めたという。
むろん、すべての元請け業者が理解してくれないわけではない。運送会社同士だからこそ、現状を分かり合うことができ、運賃値上げや待機時間の削減を積極的に働きかけてくれる元請け業者も存在する。だが元請け業者のなかで、そうした企業が多いわけでもない。
同社は、長距離便をなくし、下請けの仕事を減らした分、売り上げが低下した。しかし、法令を遵守し、利益がきちんと出せる仕事に特化することができている。社内のドライバーのなかで泊まり勤務をする人が、ぐっと減った。
社長は、これらの取り組みをする前にドライバーに望む働き方を尋ねていた。比較的若い30代のドライバーたちは、「給料よりも自分の時間がほしい」「その日のうちに家に帰りたい」と考える人が多く、昔のように「休まなくてもいいから働きたい」という人はいなかったという。