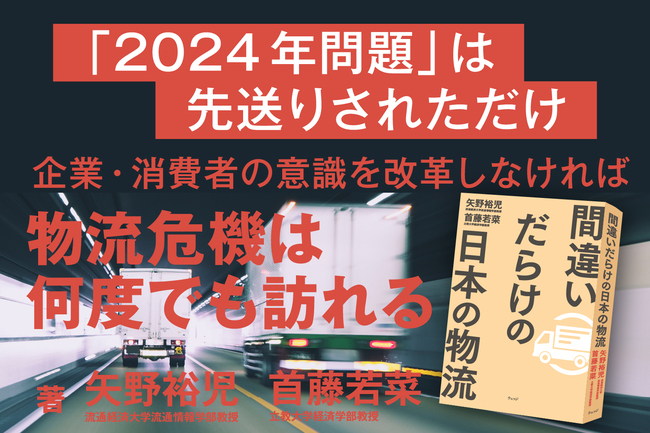多くの荷主に働きかけが行われるようになれば、運送会社も声を上げやすくなる。トラックGメンに情報提供しやすい環境が醸成されていると話す運送会社は少なくない。
下請け構造の弊害
政府は、2024年に成立した物流関連2法の改正に、元請けの業者に実運送体制管理簿の作成を義務づけることを盛り込んだ。下請け業者の名称、輸送内容を明記した管理簿を作成することで、下請け状況を可視化し、取引環境の改善につなげたいとの狙いがある。これが十分に機能するかどうかは、改正法の施行を待たなければならないが、一定の効果が期待されている。
他方で、「2024年問題」を受けて運賃や運び方の見直しを求める運送会社のなかには、そもそも下請け関係から抜け出そうと努力している企業が数多く存在する。運賃の引き上げ、荷待ちや荷役の削減を進めるには、荷主と膝を突き合わせて話し、直接交渉することが効果的なためだ。下請けにとどまる限り、法令遵守は難しいと話す運送会社は多い。
むろん元請け業者が荷主と交渉し、適正な運送を実現させているケースもある。だが、下請け関係が多層化すればするほど、それへの期待は薄まる。そもそも、長時間の待機や過重な附帯業務を負っているのが自社の社員であれば、運送会社は、従業員の声に基づき、待機時間や附帯業務の軽減を荷主と協議しやすい。
だがそれが、子会社や協力会社の社員であれば、元請け業者はそうした実態を把握しにくくなるし、荷主と協議する動機も弱まる。ましてやグループ外の企業の場合やスポットで依頼した場合、多層的な下請け構造のなかでどこの会社の誰が荷物を運んでいるのか分からない場合には、荷主との協議が遅れることは想像に難くない。
また、ヒアリング調査では、下請け構造が運賃の引き上げを難しくしていると述べる運送会社が多かった。「2024年問題」に対応するために、多くの中小の運送会社は値上げ交渉に踏み出した。しかし、大手の元請け業者が、より安い運賃で営業活動を行うことで、せっかく値上げできた仕事が根こそぎ持っていかれるという声が、全国各地で聞かれた。
元請け業者が、いかにして安い運賃を実現できているのかは、分からない。だが、少なくない運送会社が、改善基準告示を違反しなければ実現できないはずだと話す。それゆえ、ワークルールに反した運行に対する指導や勧告は、実運送を担う事業者のみならず、元請け業者にも及ぶようにしなければ、労働環境の改善は望めないと主張する運送会社が少なくない。