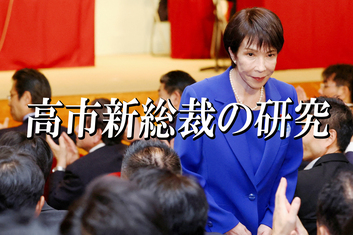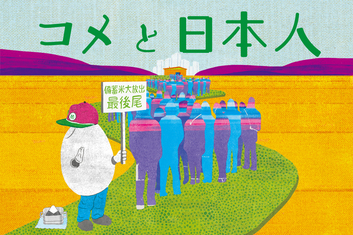スギ材は木材加工場に含水率が高いと嫌われているくらいで、生立木(せいりゅうぼく、生きている立木)は燃えにくいと思われる。アカマツの生立木も簡単に発火するとは思えないが、一旦燃え始めると樹脂(松脂・まつやに)を含んでいるので火力が強く要注意だ。
スギの人工林内にたまったスギの落葉も延焼に一役買っただろう。そもそもスギの落葉は焚き付けに最適で、薪の着火によく利用されていた。山村での生活に欠かせない便利なものなのだ。
こうした落葉は、かつて里山で自給自足的生活をおくっていた人々にとって貴重なもので、残らず採取されて林床はきれいに清掃されたような状態だった。また枯れ木もすべて燃料に利用され、燃えるものがなくて山火事が起きにくい状態に保たれていた。
現在のように、山間部の著しい人口減少と石油やプロパンガスの普及によって、林内には枯れた落葉落枝が堆積し、冬には着火剤の集積所のようになってしまっている。
このような落葉落枝は腐ると養分になるので、樹木にとっては好ましい状態なのだが、山火事のあと地表火が消えても、表面下で残火・埋火(うずみび)となってくすぶり続ける厄介ものである。なかなか鎮火・鎮圧宣言ができない理由である。
困難な山火事の消火
大船渡市の山火事では、他の都県から多数の消防車と消防隊が応援に駆け付け、山中に分け入り昼夜分かたぬ必死の消火活動、自衛隊の大型ヘリによる海水のピストン散布も行われた。半島なので、水利には恵まれているし、比較的に道路も整備されていて、消火の条件は一般の山林に比べれば相当よいのだが、それでも結局雨を待つしかなかった。
山林の多くは消防車の入らない、しかも水利が悪いから、消火といえば昔から写真7のジョットシューターという消火器具である。背中の水タンクに20リットル程度の水を入れ、ホースの先のノズルで散水する。チョッキ状のウォータージャケットという製品もあるようだが、とにかく山中では人力だけが頼りなのだ。
登山道さえない急峻な斜面を20キログラムの水を担いで駆け回るのだから、疲労困憊する。しかも煙に巻かれ、火に囲まれる恐れもある。人力消火は決死的作業なのである。
したがって実際は、残火処理程度にしか使えないが、20リットルなんてあっという間になくなる。すぐに斜面を駆け下りて給水してまた登る。まったく効率の悪い仕事なのである。
山林消火の決め手は雨乞いしかない。今回もまとまった雨・雪が降ってよかった。