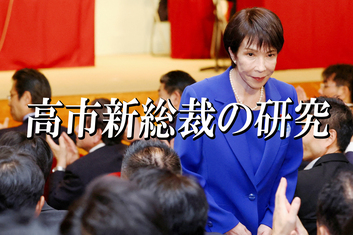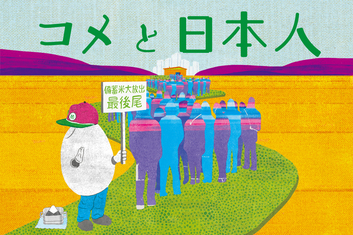被害状況から見えるもの
写真8は鎮圧後の状態である。スギ人工林の大半が見事に焼けて炭化したまま立っている。樹木上部の枝や葉が燃える樹冠火となったらしく、真っ黒になっている。しかし、尾根筋の広葉樹林は燃え残っていて、そのコントラストが著しい。
また、皆伐地の枯草が焼けて真っ黒になっているのに、隣接するスギ林も広葉樹林も樹冠火にまでは至っていない箇所もある。おそらく林内は地表火が走っていると思われる。もちろん根元部分が焼けた(写真1)だけでも樹木は相当のダメージは受けており、木材としての商品価値がなくなったものも多いはずだ。
しかし被害区域の2900ヘクタール全部が丸焼けになったわけではなく、外見は森林として残っている部分が多いので、一番心配される土砂流出防止などの公益的機能の全面的消失はとりあえず回避されているようだ。
空襲や原爆にあって生き残った戦災樹木もあるぐらいだから、この大火後でも生き続ける樹木は多いはずだ。復旧に当たっては、生き残った樹木の根系を大切にして、機能低下を起こさないよう慎重に進めるべきである。
特にこの地域で心配なのは海洋への影響である。被災地の周囲はすべて海だから、いわゆる魚付き機能は高いはずである。森林から流れ出る腐葉土などは海藻の栄養となり、昆虫は魚類の餌になるので、森林と海の生態系は密接な関係にある。
とりあえず大量の炭化物が流出するだろうが、これが海水を汚染するとは言い切れない。かえって浄化・活性化するなどよい結果をもたらすかも知れない。今後の研究に期待したい。
林地の方はどうなのだろうか。かつて山間部では焼き畑農業が行われていたが、草木灰が肥料になってよい作物が収穫できた。それであれば植樹をすれば樹木の成長もよいと思われるがどうなのだろう。研究者にとっては魅力的なフィールドかも知れない。
ちょっと気になるのは、シカによる食害である。大船渡市の北端にある五葉山(ごようさん)は東北地方きってのシカの生息地で、昔から森林被害が激しかった。最近はシカの分布域も広がっているので、山火事の焼け跡に草本類が繁茂すれば、これを好餌とするシカたちが大喜びで集まってくる可能性もある。そうなると再造林も天然更新もなかなかはかどらないだろう。