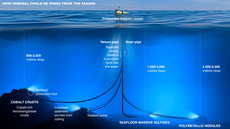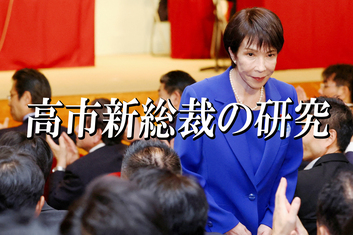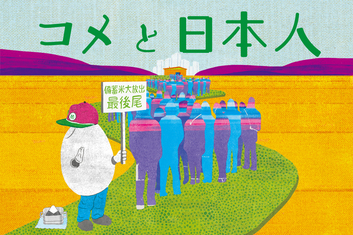山火事の予防方法
最後に山火事を拡大させない方法について述べたい。
植栽してから伐採まで何十年もかかる林業で一番怖いのは山火事である。せっかくの投資と愛情込めて行った労働の成果が一朝にして灰になるのだ。だから大規模所有者や国有林では予防措置が取られていた。
それは防火線・防火帯というもので、山の尾根筋や所有界をある程度の幅で伐開して空き地をつくり、山火事の延焼を防ぐのだ。だだし、毎年のように草刈りをしないと効果が維持できないのが難点である。
保護樹帯という広葉樹の帯も効果がある。特に常緑広葉樹は針葉樹よりも燃え難く、林床が湿潤で植生も多い。
設置場所は防火線とほぼ同じで、山火事だけでなく防風効果もあり、生物多様性も高くて、防火線のように草刈りなど手入れは必要ないから、優れものである。実際経験したことだが、人工林から延焼してきた地表火が保護樹帯で見事に消えたことがある。
今回は、森林だけでなく多くの住宅が延焼してしまった。住宅や漁業などの関連施設だけでも最小限守りたい。それならば、住宅や施設の周りに、いわゆる軒先に森林が迫っている状態を解消するため、防火帯を設ける方法はある。しかし、これも毎年草刈りなどのメンテナンスが必要だし、刈った草も運び出さないといけない。
そこで保護樹帯と同じ考えにたち、樹木で防火垣をつくるのだ。主に南日本では、サンゴジュが防火樹として知られているが、アカガシ、マテバシイなどのシイ・カシ類、ヤブツバキ、モチノキ、タブノキなど主として常緑広葉樹で樹皮が厚く含水率の高い樹種が該当する。
これらを建物の周囲に垣根として植えれば防火効果があるし、見栄えを気にしなければほとんど剪定も必要ないだろう。暖帯林の樹種が多いが、岩手県沿岸部にはタブノキが自生しているし、適地かどうか検討した上で利用するとよい。