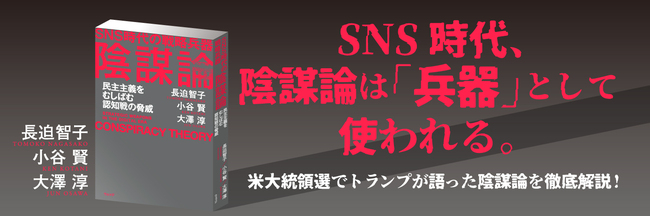「ディスインフォメーション」とは、何なのか
2016年のアメリカ大統領選挙におけるロシアの選挙干渉が注目を集めて以来、ロシアや中国による情報戦が拡大するにつれて、ディスインフォメーションという言葉が頻繁にメディアに登場するようになった。
しかし、一部の国では、ディスインフォメーションと同様の文脈で「フェイクニュース」という語を使用している。日本はその代表例であるが、単なる誤報とは異なる、国家安全保障の観点から外国の影響力工作を論じる際には、フェイクニュースという言葉は妥当ではない。フェイクニュースという言葉は、「フェイク」という語から虚偽の情報だけを指すことになってしまう。
同様に、日本でディスインフォメーションの訳語として当てられている「偽情報」についても、「偽」のニュアンスの採用は妥当ではないと筆者は考えている。ディスインフォメーションは複雑な地政学的目的に基づく影響力工作の一部であるため、これらの表現では脅威の全体像を見失うこととなる。
ヨーロッパ連合(EU)のヨーロッパ評議会の報告書では、国家主体による影響力工作だけでなく、過失による虚偽情報の流布も含めた状況を「情報騒乱」と呼び、そのような状況下での情報類型を「誤情報(Misinformation)」「偽情報(Disinformation)」「悪意の情報(Malinformation)」の3つに分けて示している。
同報告書では、ディスインフォメーションを「意図的に公衆に危害を加えたり、利益を得たりする目的で設計、提示、宣伝されたあらゆる形態の虚偽、不正確、または誤解を招く情報」と定義している。この報告書では、ディスインフォメーションは虚偽の情報をベースに構成されるという考え方となっている。
日本国内では、「Disinformation対策フォーラム」による定義が代表的だが、「あらゆる形態における虚偽の、不正確な、または誤解を招くような情報で、設計・表示・宣伝される等を通して、公共に危害が与えられた、又は、与える可能性が高いもの」 という記述はEU報告書に近しい。