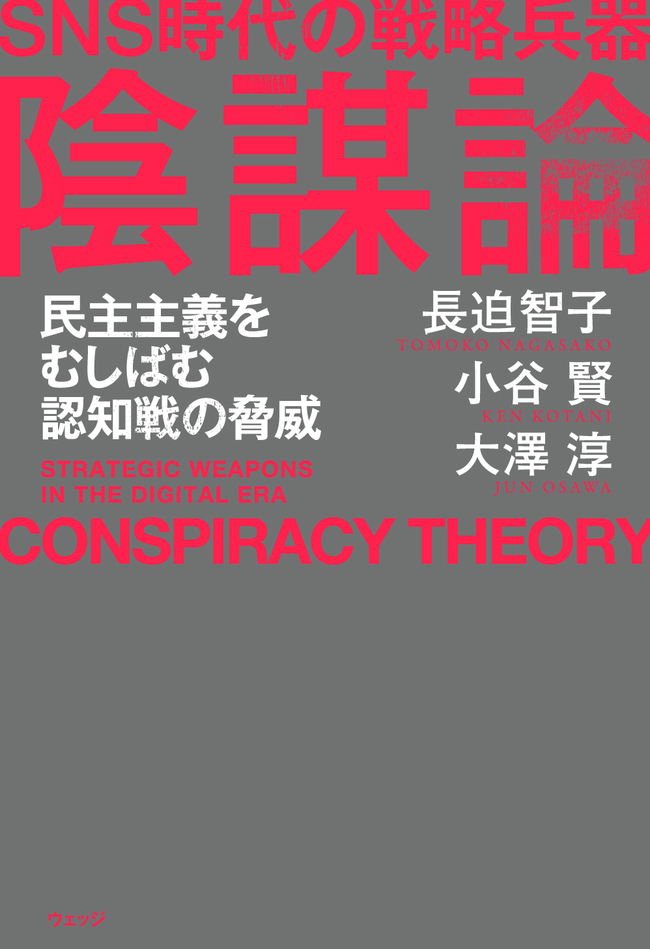陰謀論は真偽が混交しているからこそ
強い拡散力を有している
しかし、ディスインフォメーションを用いた工作では、時には真なる情報も含まれることがある。例えば、アメリカ国家情報官室(ODNI)の報告書によれば、2016年のアメリカ大統領選挙ではロシア軍の諜報機関(参謀本部情報総局〈GRU〉)が、ハッカーグループ「Guccifer 2.0」と内部告発サイト「DCLeaks.com」を利用して、民主党選挙委員会をハッキングして、メールなどの情報をリークするとともに、それを基にSNSで民主党候補のヒラリー・クリントンを貶める言説が形成されるという工作があった。このリーク情報は、本来であれば表に出ないはずの情報ではあったが、虚偽情報ではなく真の情報である。
そして、攻撃側の戦略としても、真偽の双方の混交やサイバー攻撃などによるリーク情報の活用が明言されていることにも注意が必要である。元ロシア連邦保安庁(FSB)の著者が執筆したロシアの情報戦に関する事典では、ディスインフォメーションのオペレーションは、「虚偽の情報、噂、幻想の流布」、「機密情報の『漏洩』を組織すること」、「特定の出来事や事実の誇張、矛盾するメッセージの流布」、「統一された計画に基づき、個々の活動を調整する」、「真実と嘘の比率を注意深く調和させる(もっともらしい情報を最大限に利用する)」、「真の意図、目標、自勢力(支持者)が解決すべき課題を、義務的に巧みに隠蔽する」といった手法を組み合わせることと整理されている。
ロシア自身が展開する陰謀論や悪用しているQアノンの陰謀論も、そこには誤った情報や害意のある情報、誤った関連づけなどが含まれるディスインフォメーションの一つではあるが、リーク情報を活用し真偽の情報を巧妙に混在させているからこそ、実際にそこに陰謀があると多くの人に感じさせ、強い拡散力や扇動力を有しているのである。
この観点からディスインフォメーションの再定義を行えば、「社会、公益への攻撃を目的とした害意のある情報で、情報自体が偽であるだけでなく、情報自体は真であるが誤った文脈や操作された内容で拡散されるものなど、真偽どちらもあり得る情報」と定義し得る。「偽情報」と訳されるディスインフォメーションであるが、真なる情報も戦略的に組み合わされていることに留意が必要である。
長迫智子「情報操作型サイバー攻撃の脅威(1) ―ディスインフォメーションを利用した情報戦の現状と課題」『CISTEC Journal』、第211号、155-163頁、2024年5月。
長迫智子「情報操作型サイバー攻撃の脅威(2) ―第6の戦場としての認知領域」『CISTEC Journal』 第212号、167-177頁、2024年7月。