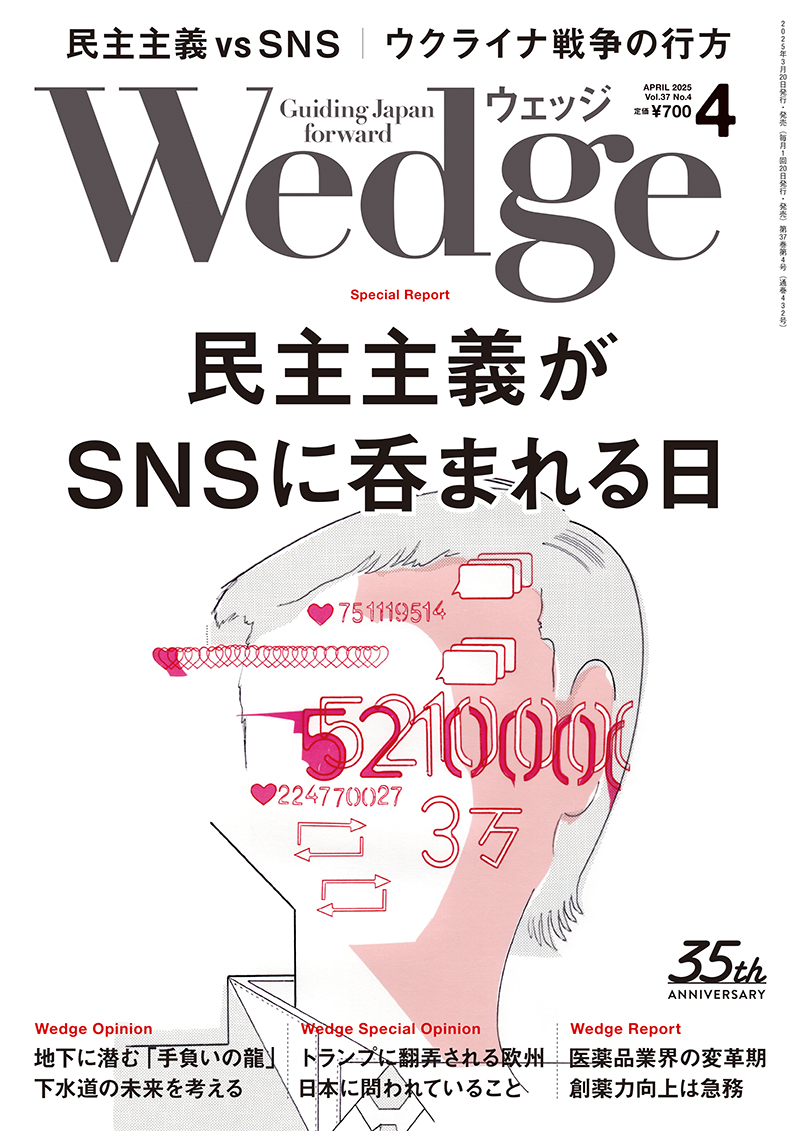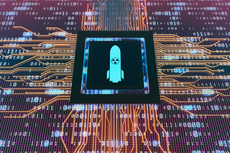明治維新と敗戦で忘却された
江戸の村の民主的傾向
1863(文久3)年、信濃地方の佐久郡下海瀬村(現・長野県佐久穂町)で行われた名主と組頭選びに関する文書には入札の様子が詳しく記録されている。『信濃の風土と歴史4 近世の信濃』(長野県立歴史館編)によると、まず台帳(有権者名簿)をつくり、人数分の札(投票用紙)が有権者に配られ、その札に本人確認の割り印を押した上で、候補者の名前を書いて投じていた。投票は戸主に限られる制限選挙ではあるが基本的な仕組みは今と同じだ。
また、当時の台帳には女性3人が登録されている。女性も戸主であれば投票権を与えられたのだ。同様のことは近世後期の信濃地方の各地に見られたという。一定の条件下では男女同権だった。さらに下層農民への投票権拡大も確認されている。
入札による村役人の選出は、幕府や各藩が作った統一的な制度ではなく、それぞれの村で平等化を求める試行錯誤の結果、生み出されたものである。世襲制が続いた村も存在する中で、この自然発生的な入札を一律な制度にしようとした動きもあった。旧布施市(現・東大阪市西部)の地域史によると、1790(寛政2)年とその翌年、荒川村三ノ瀬分の百姓代の実父、又右衛門が、寛政の改革を行っていた老中の松平定信に上書を提出している。
その上書では村政の現状について、世襲の結果、幼少者や素行不良者までが庄屋を務めている例が多いとして、選出方法の改革と、組頭の権限拡大を提案している。具体的には、入札により票の多い者を庄屋として任命し、同数の場合は所有農地の生産量が多い方とする、百姓代は5人の組頭の中から輪番で選ぶ、というものだった。
こうした江戸の村の民主的傾向は明治維新、敗戦を経て忘れ去られることになる。
※こちらの記事の全文は月刊誌「Wedge」2025年4月号「民主主義が SNSに呑まれる日」で見ることができます。