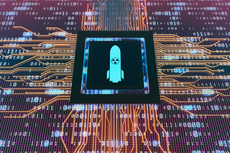「民主主義とどう向き合えばいいのか?」
最近、よく耳にするこんな問いは、往々にして迷路の入り口になる。欧米で市民革命などを経て、国民主権、基本的人権の尊重などを基本理念として発展してきた─。こんな定型的で理想的なイメージを起点として思いをめぐらした結果、私たちは「その実現に向かって進むべきだ」と答えがちだ。そして「では、具体的に何をすれば?」という難問に直面し、行き止まる。
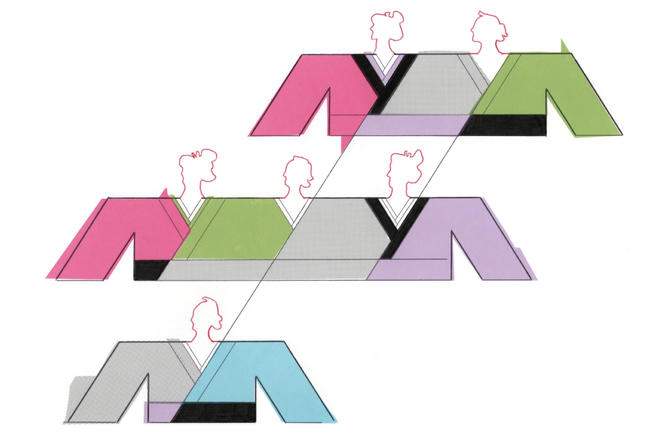
迷路に入り込まない方法の一つは、民主主義を標榜する現実の国家を吟味し、未達点に対して処方箋を考えることだ。しかし今の大きな課題は、それ以前に民主主義自体が後退、〝空洞化〟していることである。政治体制の権威主義化、社会の分断と対立。SNSがその触媒となり、内外の政治は「スマホ・ポリティクス」の様相を呈している。日本では近年の投票率の低下が選挙制度を空洞化させている。
「欧米産の民主主義をいったん脇に置き、日本の中に選挙などの具体的なシステムの源流を探る」
これが筆者の迷路迂回策だ。実は江戸時代の村々に既に選挙による代表制や権力の分立による均衡といった「民主的傾向」が存在していた。私たちの先祖が、民主的傾向をどのように生み出し、高度な自治をどう発展させていったのかをたどる作業は遠回りのようだが、日本人が今後民主主義とどう向き合うかにあたっての示唆がある。
江戸の村でみられた民主的傾向の代表例は「入札」と呼ばれた選挙の仕組みだ。当時の村は、百姓の家々でつくる集落を中心に田畑などの耕地や山などを含む広い領域を持つ共同体だった。名主(庄屋・肝煎)、名主の補佐役である組頭(年寄)、一般の百姓の代表である百姓代。現在の村長、助役、監査委員にあたる、これらの村役人(村方三役)は、田畑を持ち年貢を納める本百姓の中から入札で選ばれ、多岐にわたる村政運営を行っていた。
江戸時代初期、トップの名主は、戦国時代の地侍や土豪の末裔など社会的、経済的に優位な家系の世襲が多かった。しかし、中期以降になると本百姓間での一代交代や年期を区切った輪番などの制度が現れ、後期には入札で決める村が出現した。百姓代は年貢の配分などをチェックする役割で、一種の権力分立だった。そして、組頭や百姓代の多くは、本百姓らによる村政改革運動である村方騒動によって生まれている。