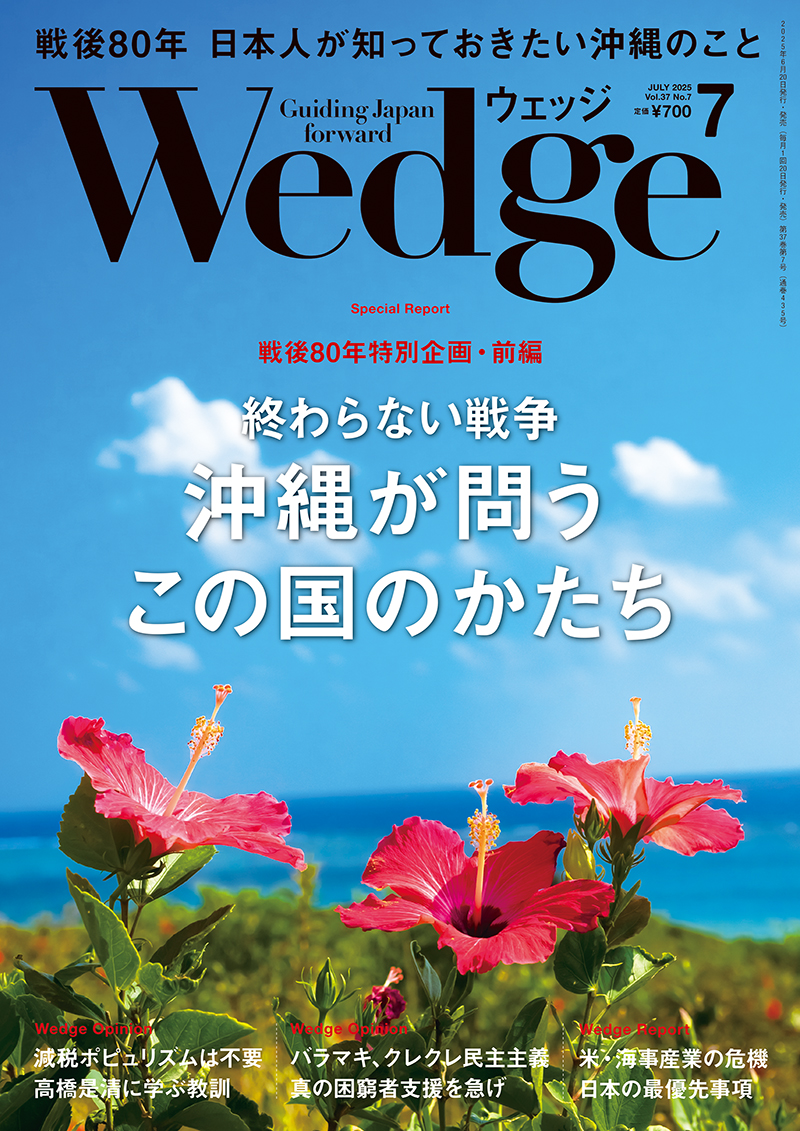清掃には時間の制約がある。しかし、こびりついた汚れを見ると「新幹線を常にきれいに保ちたい」というプライドが刺激されるという。時間内にいかにきれいに磨き上げるか。そこに各人各様のコツがある。本多さんの場合は、先頭部の表面に薬剤をかけて時間を置く。いちばん汚れている箇所にまず薬剤をかけた後、ほかの部分のブラシがけを行っている間に薬剤を十分浸透させ、頃合いを見計らってブラシでこすると、汚れがきれいに取れるという。汚れの状態によって薬剤を浸透させる時間が異なる。そのタイミングの見極めが〝匠の技〟なのだ。
トイレの巡回は2時間おき
仕事の原動力はどこにあるか
手嶌さんは駅舎の清掃を担当していた時期がある。「いちばん大変だったのは?」と尋ねると、「トイレ掃除です」。駅のトイレは人の出入りが激しい。一度きれいに磨いても、しばらくすると汚れてしまう。
「お客様がいらしても、『すみません、ちょっと清掃させていただきます』と断りを入れて掃除をします。とてもきれいな状態に仕上げるのは無理でも、全体的にきれいな状態を保つように掃除をします」
博多駅2階のコンコースは北側と西側の2カ所にトイレがある。1日に何回くらいトイレ掃除をするのだろうか。手嶌さんは「通常は2時間おき、多客期には1時間おきに巡回しています」と答えた。女子トイレは行列ができていることが多い。その行列を「すみません」と詫びてかき分け、個室の中を覗いてトイレットペーパーが切れていないか確認する。切れていれば、「お客様をあまりお待たせしないようにすぐに補充します」。
トイレをきれいな状態で提供したいという使命感が仕事の原動力だが、それだけではない。ときどき清掃中に利用客から「いつもありがとう」と声をかけられることがある。手嶌さんも「お気をつけて行ってらっしゃいませ」と返す。そんなちょっとした声の掛け合いが楽しく、仕事のモチベーションになるという。今度、駅のトイレやホーム上で清掃する彼らの姿を見かけたら、感謝の気持ちを伝えようと思った。