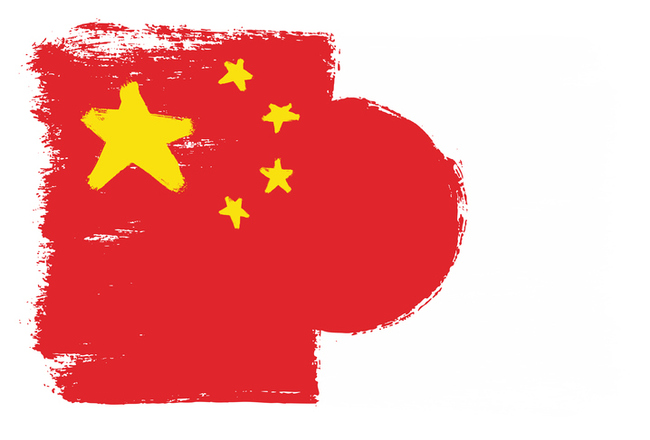高杉らを乗せた千歳丸による上海訪問から10年を経た明治5(1872)年、明治政府の外務卿・福島種臣は日清修好条規批准書交換のために清国に旅発つ。両国の国交が開かれたことにより、伊藤博文を筆頭とする政治家、外交官、軍人、学者、文人、経済人など多彩な明治人が大陸を訪れ様々な思いを綴っている。彼らの多くは“表玄関”から清国を訪れ、外交・経済・文化などを中心に“大上段”から清国を捉え、両国関係を論じた。
日清修好条規批准書交換は、じつは名も無き市井の人々にも大陸旅行の機会を与えたのである。それまで書物でしか知ることのなかった「中華」を、彼らは自ら皮膚感覚で捉え書き留めようと努めた。
かりに前者を清国理解における知性主義とでも表現するなら、後者は反知性主義と位置づけられるだろうか。これまで知性主義による清国理解は数多く論じられてきたが、反知性主義のそれにはあまり接したことがない。
歴史教科書で扱われることなどなかった明治人による反知性主義的清国理解を振り返ることは、あるいは知性主義の“欠陥”を考えるうえでの手助けになるのではないか。それというのも、明治初年から現在まで知性主義に拠って律せられてきた我が国の一連の取り組みが、我が国に必ずしも好結果をもたらさなかったと考えるからである。もちろん反知性主義だからといって、その結論が現在の我が国メディアで喧伝されがちな中国崩壊論に、あるいは無条件の中国礼讃論に行き着くわけでもないことは予め断わっておきたい。
※なお原典からの引用に当たっては、漢字、仮名遣いは原文のままに留め、変体仮名は通常の仮名(たとえば「ヿ」は「こと」)に、カタカナはひらがなに改めることを原則としておく。
「木材調査」を目的に清国に渡った日本人
原田藤一郎が小樽を後に上海に向ったのは、日清戦争勃発2年前の明治25(1892)年1月半ばだった。厳寒期の北海道である。さぞや寒い旅立ちであったろう。
上海滞在後、江蘇省・山東省・河南省を経て北京、天津へ。さらに満州への入口である山海関を抜け「渤海の沿岸を周り營口(即ち牛莊)に出て北行」し、鴨緑江沿いを朝鮮へ。その後、明治26年1月20日にロシア領に抜け、ウラジオストック・沿海州沿岸から樺太を経由して北海道の宗谷へ向かう。だが暴風に押し流され樺太東海岸に漂着し、幸運にも「一命を保持して札幌に歸着」したのが明治26年9月14日だった。
この間、ことばは覚束ない。頼りといえば限りない好奇心とクソ度胸、それに頑丈な2本の脚のみ。運を天に任せ、興味の赴くままに大陸を踏破するしかなかった。
北海道で氷の販売に携わっていた原田が清・韓・露の3国を踏破・調査したのは、関係業者から「清國木材調査」を依頼されたからだという。時期からして日清戦争を想定しての“敵情調査”とも考えられる。
原田が著した『亜細亜大陸旅行日誌幷清韓露三國評論』(明治27年 嵩山堂)に従って、「日數一年八ヶ月歩走の里程一万四千六百八十清里水路二千三百六十哩旅費總計三百圓」に及んだ原田の旅を追体験してみたい。
日清戦争を前にした「時代の雰囲気」
最初に上陸した異国の大都市・上海は、「東洋に於ける人間の博覧會塲」であった。
夥しい数の「清國下等人種」を前にして、「噫清人は人間にあらざる乎」と第一声をあげる。「其不潔と臭氣」に辟易としながらも街を歩くと、上海は横浜や神戸とは違っていて「外國人が一隅に避在する」街ではなく、むしろ外国人のための街であることに気づく。そこに「居住する清人は窃盗を以て恥辱と」しないばかりか、「些少の隙あらば假令同居人の物品と雖も之を窃取するを以て常とす」るほど。だから上海では「盗みしものより寧ろ盗まれしものヽ不注意を責む」。それほどまでに物騒で、「人情は浮薄」である。
上海で我が物顔に振る舞う「外人等が清人を遇するは全く對人間の禮節な」く、まるで「牛馬と同視する」ほど。「外人は無遠慮にも靴を以て彼等を蹴り或は鞭韃する」。どうやら虐待が日常茶飯事だったようだ。そこで「噫清人は何が故に斯くも柔弱なるか」と隣国人の惨めな姿を嘆いている。
だが、そんな「清人」でもイザとなったら力を合わせ外人に立ち向かう。圧倒的な数で攻め立てられたら、普段は足蹴にし、あるいは鞭打つ外人であっても、多勢に無勢と逃げ出すしかない。ところが「日本人に限り假令一名となるも決して遁走を爲さず短刀其他の武器を以て實際に敵手を切る」。上海在住の日本人は、かくも野蛮で無鉄砲だったのか。
当時、上海の「日本人の居留者」は800人から1000人を数えたようだが、「郵船會社三井物産樂善堂其他二三の旅店と二三の商店を除けば」、まともな商店は見当たらない。正業に就いている日本人居留民を最大限で200人と見積もった原田は、「他の六百名乃至八百名」の「大半は賤業の淫婦にあらざれバ、無識の無頼漢」と推測した。「無識の無頼漢」は「賤業の淫婦」でメシを食っていた女衒であり、彼らの用心棒だっただろう。
原田の推測する上海在住日本人の人口構成から判断して、「賤業の淫婦」の顧客の多くは日本人ではなかったはず。ならば舐められたら商売はあがったり、である。「無識の無頼漢」が街頭で一歩も引かずに武勇伝を繰り広げたとしても、強ち全面否定されるものではない。ここに日清戦争を前にした時代の雰囲気が感じられる。
ところで原田は、清国商人の外国商人相手の仕事ぶりを「常に他の落目を見て己を利する」ことに長けた「我國に於ける投機商と質屋」のようなものと捉えた。