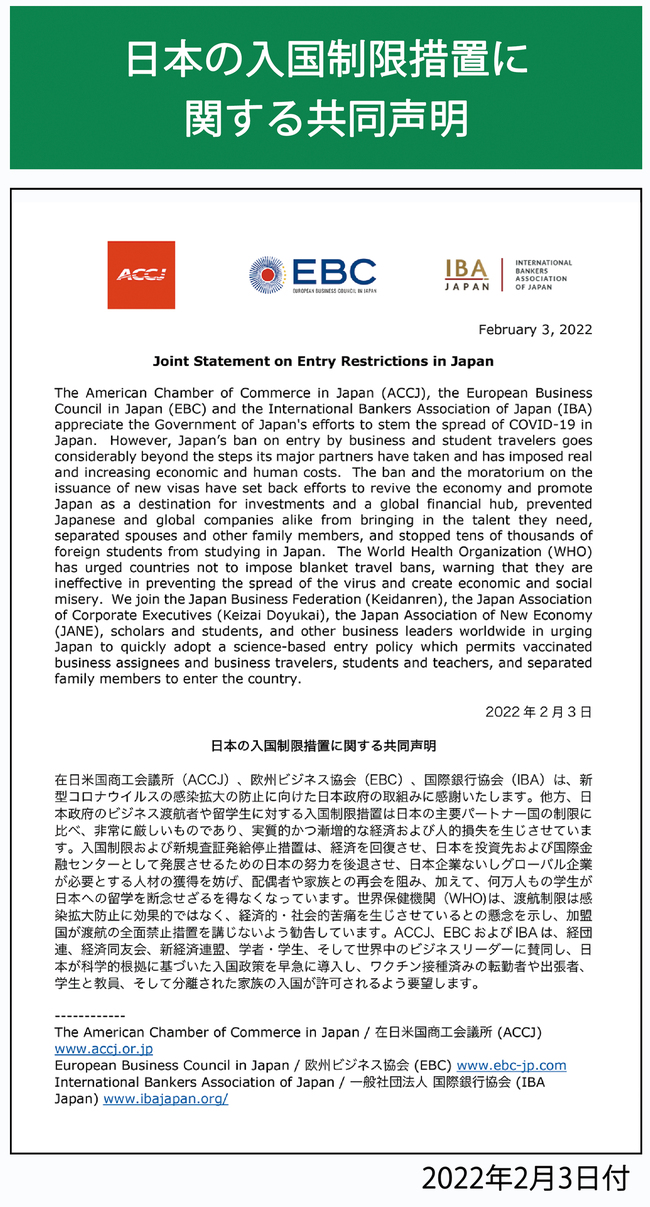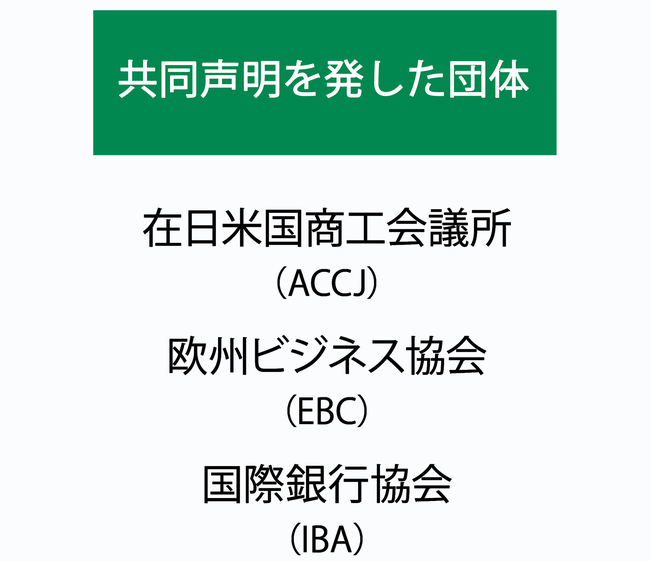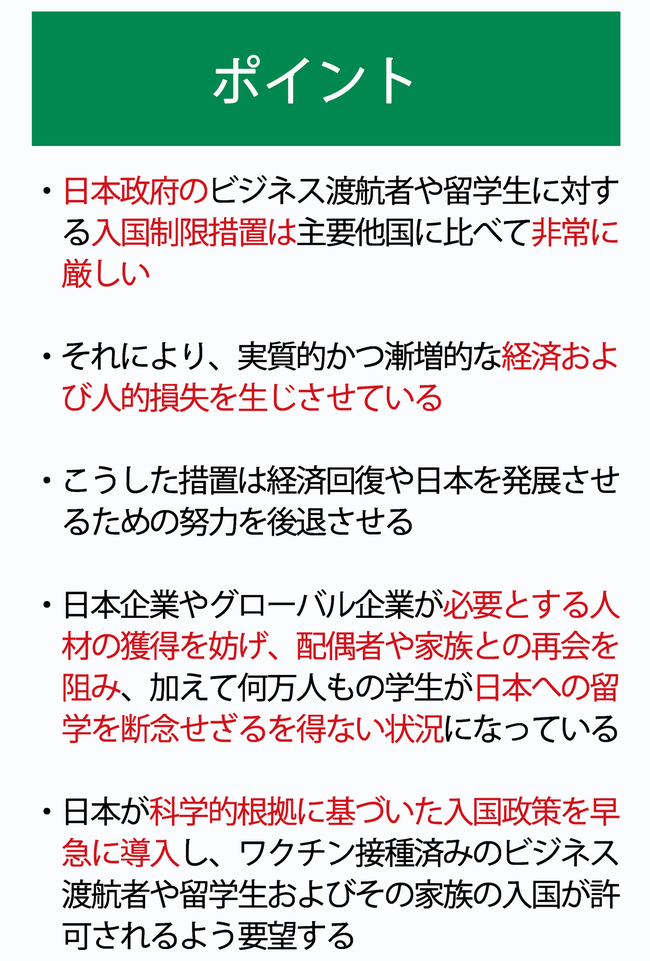コロナ鎖国を長引かせた日本には「外交」の視点が欠如していた。知日家・親日家の育成に向け、国際交流の価値を再考するときだ。「Wedge」2022年5月号に掲載されているWEDGE SPECIAL OPINION「日本第一主義の「コロナ鎖国」 これでは世界から見放される」では、そこに欠かせない視点を提言しております。記事内容を一部、限定公開いたします。全文は、末尾のリンク先(Wedge Online Premium)にてご購入ください。
たかが2年、されど2年である。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日本政府が水際対策を導入したのは2020年2月のことだ。以降、その厳格さから「コロナ鎖国」とも指摘され、世界から批判を浴びた。
日本政府観光局(JNTO)によれば、19年に留学、ビジネス、観光などの目的で日本を訪れた外国人は3188万人に及ぶ。それだけ多くの外国人が日本という国に関心を持ち、文化や空気感に触れたいとの証しと言える。
だが、政府は世論の反発を恐れ「日本さえ安全ならばいい」とばかりに〝自国中心主義〟で国を閉ざした。それでもウイルスがすぐに消えてなくなることはない。むしろ、長期にわたり人々の往来を止めたことによる国際交流やビジネス、観光、外交面での損失は甚大だ。このままでは日本は将来、大きな〝ツケ〟を払うことになる。
良質かつ強い危機感の下、一刻も早く「鎖国」状態を改め、日本のプレゼンス向上やファン・仲間づくりの再開に踏み出すべきだ。今こそ政府の確固たる決断と政策が求められている。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日本政府が水際対策を導入したのは2020年2月のことだ。以降、その厳格さから「コロナ鎖国」とも指摘され、世界から批判を浴びた。
日本政府観光局(JNTO)によれば、19年に留学、ビジネス、観光などの目的で日本を訪れた外国人は3188万人に及ぶ。それだけ多くの外国人が日本という国に関心を持ち、文化や空気感に触れたいとの証しと言える。
だが、政府は世論の反発を恐れ「日本さえ安全ならばいい」とばかりに〝自国中心主義〟で国を閉ざした。それでもウイルスがすぐに消えてなくなることはない。むしろ、長期にわたり人々の往来を止めたことによる国際交流やビジネス、観光、外交面での損失は甚大だ。このままでは日本は将来、大きな〝ツケ〟を払うことになる。
良質かつ強い危機感の下、一刻も早く「鎖国」状態を改め、日本のプレゼンス向上やファン・仲間づくりの再開に踏み出すべきだ。今こそ政府の確固たる決断と政策が求められている。
新型コロナウイルス感染症の発生から3度目となる春の訪れとともに新年度が始まった。
だが、かつては多くの外国人観光客で賑わっていた地域や、国際的事業の多い企業、国際教育交流の盛んな大学などでは、外国から訪れる人の数がまだまだ少ない状況が続いている。
日本はコロナ禍を通じて、外国人の入国に関し、世界でもトップクラスの警戒度を維持し、厳格な水際対策を行ってきたからである。
この間、海外の日本研究者やビジネスパートナーの間では、日本の鎖国政策に対する不満が鬱積していった。2020年冬には、多くの国が国際交流を制限したこともあり、厳しい水際対策にも一定の理解を得やすかった。筆者の住む米国内の大学関係者の間でも、日米の学生や研究者の交流が途絶えることにさまざまな懸念はあったが、当時の状況からは、しばらくの間、訪日が困難な状況が続くことは仕方がないという認識の方が強かった。
しかし、21年11月以降、日本の鎖国政策が国際社会でも際立って厳しい制限であったことや科学的根拠に乏しかったこと、さらにその状態が何カ月も続いたことなどから、相次いで批判の声が聞かれるようになった。揚げ句には海外の日本研究者が連名で「開国」を求める声明を出したり、在日米国商工会議所や在日ドイツ商工会議所などからも水際対策緩和を要請される事態となった。最終的には、こうした声を受けて水際対策の緩和が実現し、岸田文雄首相はその「聞く力」を示したのだが、なぜこれほど時間がかかったのだろうか。
複数の海外経済団体からも日本の
「開国」を望む切実な声が上がった