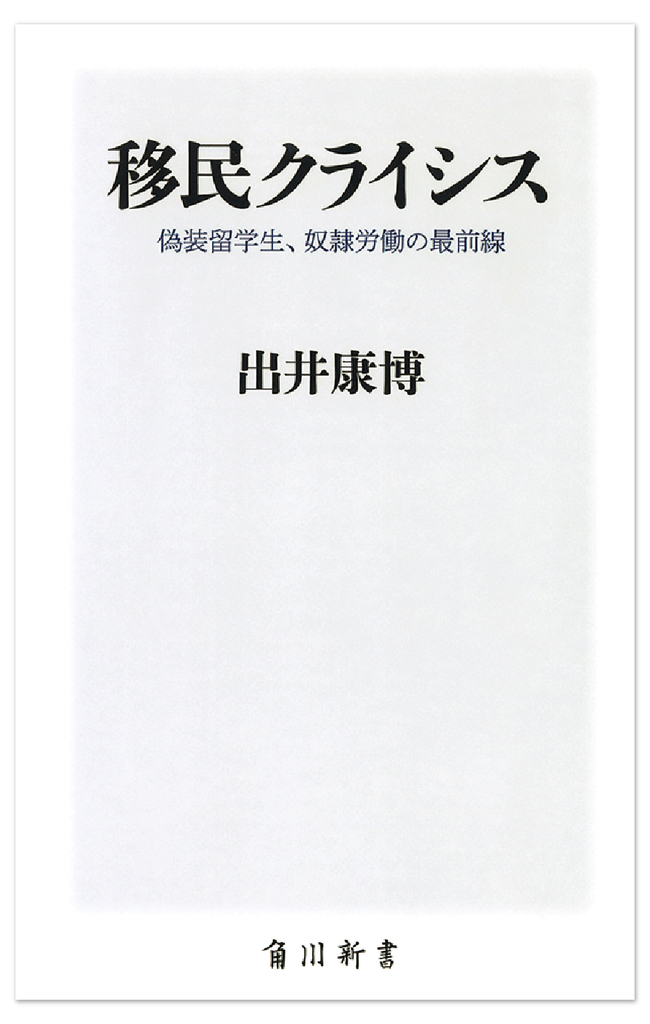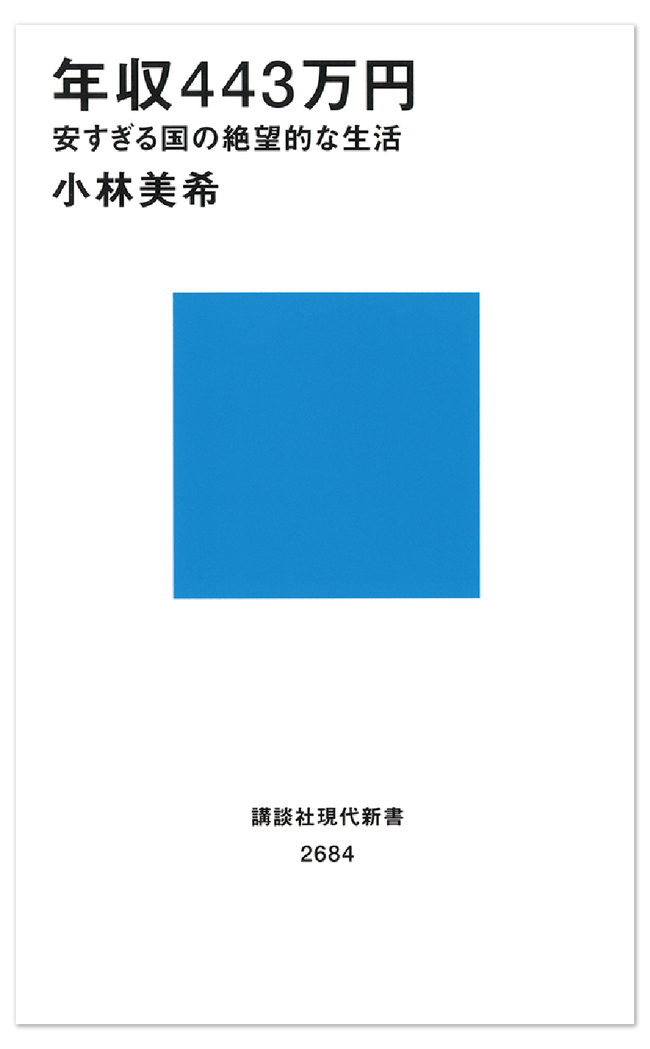出井 僕が就職したのは、平成になって2年目の90年です。当時、日本経済新聞が英字新聞を日刊化していこうとしていて、英文記者要員として入社しました。もともと、僕は戦場ジャーナリストになりたかった。オリバー・ストーン監督の映画やらを観て憧れていたんです。

1965年岡山県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。英字紙「日経ウイークリー」記者、米国黒人問題専門のシンクタンク「政治経済研究ジョイント・センター」(ワシントンDC)客員研究員を経てフリー。著書に『ルポ ニッポン絶望工場』(講談社+α新書)など多数。
いずれ、ニューヨーク・タイムズに転職して、戦争報道でピュリツアー賞を取るというのが目標だったんですが、サラリーマンには不向きだったのか3年で会社を辞めました。
それから、アメリカにある黒人問題を専門に研究しているシンクタンクに所属しました。当時は、日本の自動車メーカーがケンタッキーやオハイオなどにどんどん工場の建設に乗り出していました。一方、アメリカ「ビッグスリー」の拠点は、デトロイト市ですよね。デトロイトは人口の8割が黒人ですが、日本の自動車メーカーが工場をつくったのは白人が大半を占める町だった。その結果、黒人の仕事を奪ったと雇用差別で訴えられるケースが相次いでいたんです。そんなことを調査するのが役目でした。
そのシンクタンクに1年勤務し、帰国後はフリーランスとして仕事を始めました。でも、やっぱり戦場に行きたいという思いがあって、ちょうど20年前の2004年、週刊誌の特派員としてイラク戦争を取材しました。行ってみると、血が騒ぎ、不謹慎ですが、楽しかった。自衛隊がいたサマワや、バグダッドのグリーンゾーンを拠点に取材しました。ただ、途中から、ふとむなしい思いにかられたんです。楽しいけど、何のためにやっているのかなと考えてしまって……。
もう30代後半で、何かひとつテーマを持ってやりたいなと思うようになっていた時、 07年に新潮社の月刊誌『フォーサイト』で外国人労働者問題の連載を持たせてもらうことができたんです。このテーマというのは、やがて国論を二分する問題になっていくだろう、そこにコミットしたいと思い取材を始め、今年で18年目になります。
小林 私が大学を卒業したのは2000年です。後で調べて知ったのですが、統計史上初めて大学生の就職率が6割を下回った年でもありました。神戸大学出身ということで、どこかには就職できるだろう思っていたのですが、100社ぐらいエントリーして50社ぐらいの面接を受けても、全く引っかかりませんでした。唯一内定をもらったのは、CMでお馴染みの大手消費者金融の会社だけでした。当時は不景気で、女性が総合職を目指すのは、まだ難しいという面もあったと思います。

1975年茨城県生まれ。神戸大学法学部卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年よりフリーに。著書に『ルポ 保育崩壊』『ルポ 看護の質』(岩波書店)、『ルポ 産ませない社会』(河出書房新社)、『ルポ 母子家庭』(筑摩書房)など多数。
結局、親に大反対されて、消費者金融は断り、大学卒業後、ハローワークに通って、6月に株式新聞に入社しました。1年後、株式新聞を退社し、毎日新聞社(現・毎日新聞出版)に契約社員として転職し、『週刊エコノミスト』編集部に記者として所属しました。
ITバブルがはじけたというのに、「企業業績はV字回復」と聞くようになって、「これっておかしくないか?」と思うようになりました。
私も含め、同世代がすごく疲れていました。新人だから覚えることもたくさんあるし、勉強しないといけないから、そうした疲れもあるかもしれないけど、同世代が感じている疲れとは、そういう種類のものではありませんでした。
決算説明会に行くと、「当社は正規雇用を減らして、利益を確保していく」という話も聞こえてきました。04年には、派遣法が改正されて1年から3年、製造業への派遣も解禁されました。こうした規制緩和が行われて、非正規労働者を生み出しやすい経済環境にしておいて利益がV字回復したというのは、ただ単に人件費を減らすことで実現しただけです。
これこそが日本経済、そして社会全体の足腰を弱めることだと思って、編集部の会議で、何度も企画を提案して、やっと実現したのが、ちょうど20年前、04年5月の「お父さんお母さんは知っているか 息子と娘の〝悲惨〟な雇用」という第2特集でした。
若者の派遣労働、非正規労働をテーマにしたのですが、読者層が中高年なので、このタイトルにしたのです。その頃、中高年の方々のお話を聞いていると「息子が就職できずにフリーターになって困っている」という声をよく耳にしていたことも大きかったです。
労働者派遣法は1986年に施行されました。同じ年に男女雇用機会均等法も施行されたのですが、結局、女性の雇用を増やしたけど、内実は「非正規で」ということだったのかなとも思えます。しかも、3年経ったら正社員にするというルールだったはずが、3年経ったら雇い止めをするに変わっていました。
「派遣は麻薬と同じ」
山田 キャリアが〝リセット〟され続ける─。これこそが、非正規雇用最大の問題点だと思います。正社員と非正規との役割分担やその労働条件を明確にして、非正規が本当に納得して働いているならいいと思うのですが、そうではなく、正社員の置き換えになっている。3年経ったら、新しい職場に行かないといけない。しかも、人間関係も一からつくり直す必要もある。同じ事務の仕事でも、会社によってやり方は違うじゃないですか。これが辛い。
ずっと派遣社員で、正社員に登用された人を知っていますが、3年ごとに「もうすぐ切られる」から、その前に職探しをする。精神衛生上も非常に不安定になると話していました。
出井 小林さんの著書を拝読していて「派遣は麻薬と同じ」という言葉を使われていました。「派遣」は、まさに外国人労働者に置き換えることができます。派遣会社が労働者を派遣することで紹介料をもらうように、技能実習生についても「監理団体」が、各種名目で企業から手数料を徴収します。そこに「利権」が生まれるわけです。留学生も同じです。留学生はブローカーにお金を払って、つまり借金を背負って日本語学校に入ります。
留学生はビザ取得時に学費を支払う経済力を証明する必要がありますが、書類の偽造が横行しています。