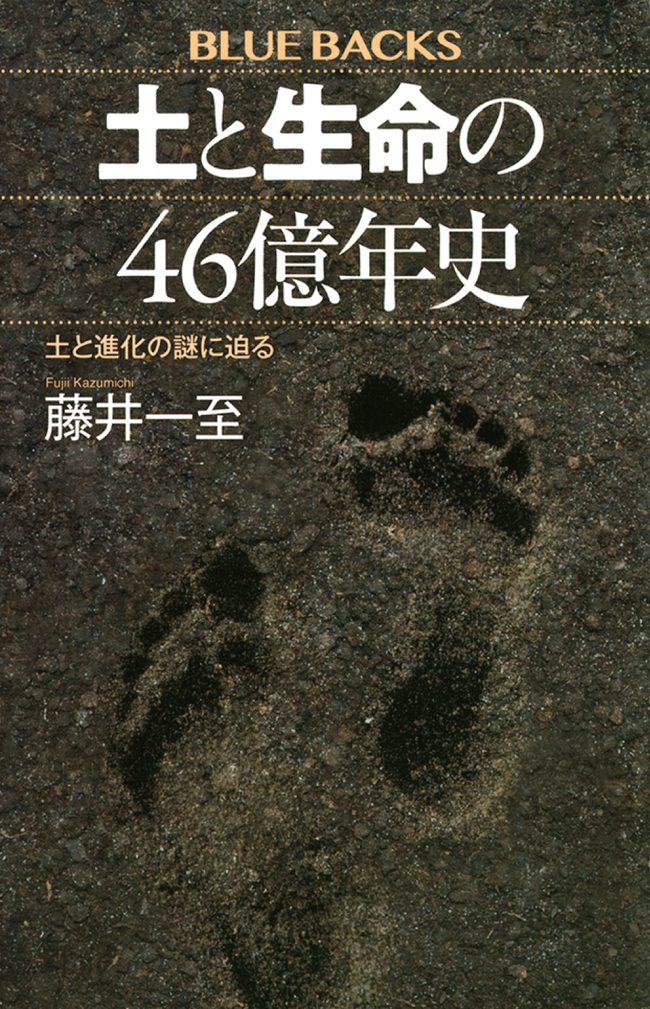日本人の主食といえばコメ。それは水田でつくられる。私たちにとって当たり前の景色は、2000年にわたる新田開発の賜物である。なぜここまで水田にこだわったのか。田んぼとは、山から流れ出す水と栄養分を海に流してしまう前に回収する仕組みである。だが、もったいない精神だけが理由ではない。
日本や東南アジアなど、森林が多く、降水量の多い場所では、土壌が酸性になる。酸性の土壌では作物が育ちにくい。歴史をさかのぼれば、詩人の宮沢賢治は、盛岡高等農林学校(岩手大学農学部の前身)に首席で入学、土壌学を学び、卒業後は酸性土壌を中和するための石灰を売る販売員をしていた。貧しい農家に石灰を買ってもらう葛藤を抱えた日々の中で『雨ニモマケズ』を詠んだのだ。原因は酸性土壌の存在だった。
平坦な土地の少ないタイ北部の山岳地帯では、「焼畑」が行われてきた。灰が土壌を中性化してくれるからだ。ただし、焼畑は3〜10年に一度しかできない。一方、田んぼに水を張ると、酸素欠乏によって土の中が還元的になり、酸化鉄が溶け始める。この反応によって、土壌が中性化し、稲に必要なリンも溶けやすくなる。しかも毎年収穫できる。5年に一度の焼畑に比べ、田んぼの生産性は15倍も高くなる。これが、日本人が水田にこだわった理由だ。
酸性の土壌がいかに人類にとって嫌われたものだったか、四大文明発祥の地を見れば分かる。メソポタミア、エジプト、インダス、黄河文明は共に乾燥地帯。土は中性~アルカリ性だ。そこを流れる大河の水を利用して灌漑農業を始めた。酸性ではない、肥沃な土と水が両立する条件が巨大農耕文明の成立には欠かせなかった。ただし、畑作の農耕文明には限界もある。メソポタミア文明は、土壌に塩類集積が起きたり、土壌が侵食されたりすることで衰退した。歴史家のヘロドトスの「エジプトはナイルの賜物」という言葉に知られるように土の生産力の回復にはナイル川の氾濫が欠かせなかった。