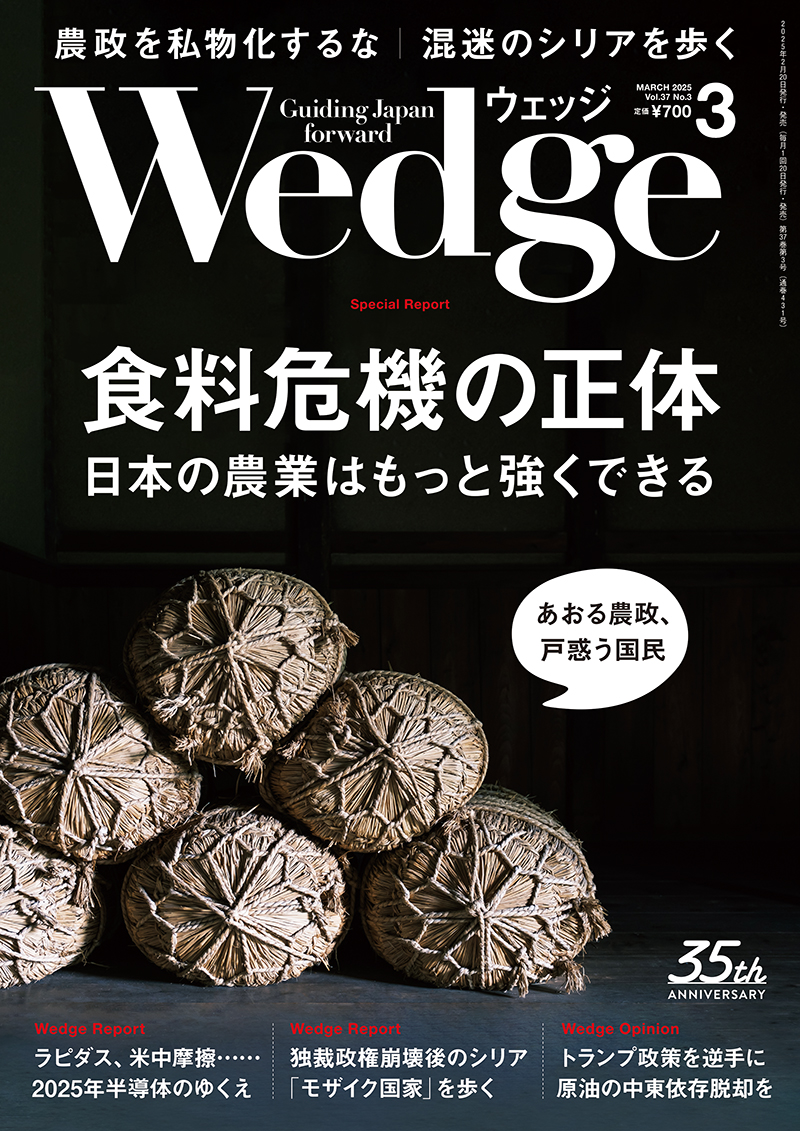極端に走らない
選択肢を減らさない
「食料安全保障」という言葉の難しさは、かつて多くの国が自国の食料自給を達成しようと植民地政策や侵略を実行した歴史が示している。国内においても、歴史や農業に関して十分な知識のないままにナイーブな極論どうしがぶつかれば、分断しか生まれない。
日本は数千年も水田稲作によって農業を継続できた稀有な国である一方で、土壌が酸性であること、大規模化に限界があることなど、強みと弱みがある。小麦や大豆など単位面積当たりの収穫量で世界平均を大幅に下回る作物の生産については適地に任せつつも、多少効率は悪くても国内でも生産は続けることでサプライチェーンを強靭化できる。少し値段は高くても国産の物を買うという消費行動も必要になる。
マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツは、米国で最大の農地所有者(11万ヘクタール)であると言われている。農地が将来にわたって安定した投資先であることを示す事実であると同時に、やはり食料や環境問題への関心があるようだ。実際、ブログには『We should discuss soil as much as we talk about coal(石炭について話すのと同じくらい土壌について話すべき)』という記事もある。
記事では、「肥料に代わる微小窒素工場:有害な亜酸化窒素を大気中に放出せずに植物に肥料を与えることができたらどうだろうか?」と投げかける。実際、BEV(ゲイツがつくった脱炭素特化型のベンチャーキャピタル)は、植物に窒素を供給しつつ温室効果ガス排出を削減できる遺伝子編集微生物を開発・販売するPivot Bio社に投資している。
「遺伝子編集微生物」と聞くと、これに限らずギョッとする人もいると思うが、微生物資材(バイオ・スティミュラント)そのものは成長産業である。実用化するかどうかはさておき、研究開発でいつも欧米の後手に回り、輸入品を高く買わなければならなくなる事態は避けたい。
食料安全保障という言葉の弊害は、自給率という数字の話になってしまうことにある。農業はただカロリーを満たせばいいものではないし、国民の約1%にすぎない農家(基幹的農業従事者)や政府に責任を押し付けられるものではない。国内の水田稲作も北米のジャガイモ生産も旅先で出会う多様な農業と地域の特産農作物の生産も日本の食料安全保障には欠かせない。地産地消と適地適作という二つの原則を尊重し、選択肢を減らさないことが必要だと考える。(談)