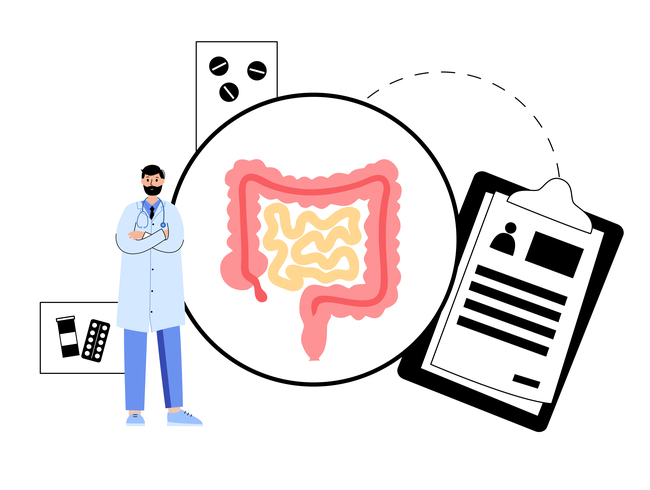
がんという言葉は、多くの人に恐怖と不安をもたらす。日本ではがんが死因の第1位で、日々多くの人々がこの病に苦しみ、がんによる死者数は増え続けている。医療技術は進歩しているものの、この現状を無視することはできない。
がんは加齢に伴って発症リスクが高まる病気であり、医療の進歩によって人々は長生きできるようになった。以前は感染症や心血管疾患で亡くなる人が多かったが、これらの病気による死亡率は低下した結果、がんと向き合う機会が増えている。
次に、生活習慣の変化も影響している。食生活の欧米化や運動不足、ストレスの増加、喫煙や飲酒は、がんのリスクを高める要因として知られている。特に高脂肪食や加工食品の摂取は、大腸がんの発症を助長することが明らかになっている。これらの生活習慣は、現代社会のストレスフルな環境とも深く関わっている。
さらに、医療技術の進歩により、無症状のうちにがんが発見されるケースが増えている。MRIやPET-CTの普及により、早期発見が可能になったが、これもがん患者の増加に寄与している。医療の進歩は喜ばしいことだが、同時にがん患者の数が増える要因にもなっている。
がん治療にはいくつかの課題がある。まず、がんの根本的な治療が難しいという点だ。がんは細胞の突然変異によって発生するため、簡単に治すことができない。特に進行したステージでは完治が難しくなり、再発のリスクも高まる。
次に、先進医療へのアクセスが遅れていることが問題もあるとされる。欧米では新しい抗がん剤や免疫療法が早く承認され、患者は最新の治療を受けられるが、日本では新薬の承認が遅れ、保険適用までの時間が長い。これによって、最先端医療を受けることが難しくなっているという。
「がん難民」の存在
また、「がん難民」と呼ばれる患者が増えていることも深刻な問題だ。日本の医療は治る可能性のある患者には積極的だが、末期の患者には消極的な傾向が見られる。多くの患者が「もう治療法はありません」と告げられ、治療の選択肢が尽きてしまうことが増えている。さらに、高齢者の増加に伴い医療費全体が膨れ上がり、財政の負担が限界に近づいている。特に高額な抗がん剤は、1人当たり年間数千万円かかることもあり、保険適用が厳しくなる可能性がある。
さて、以上を理解した上で統計による真実を話したいと思う。
2020年には約94.5万人(男性約53万人、女性約41万人)が新たにがんと診断されたが、2023年にはがんで亡くなった人が約38万人(男性約22万人、女性約16万人)に達した。これにより、がん患者の約40%が亡くなり、逆に言えば60%が生存していることがわかる。
5年相対生存率でも、男女計で64.1 %(男性62.0 %、女性66.9 %)となっており、がんになっても、生き残ることができることを統計は示している。

















