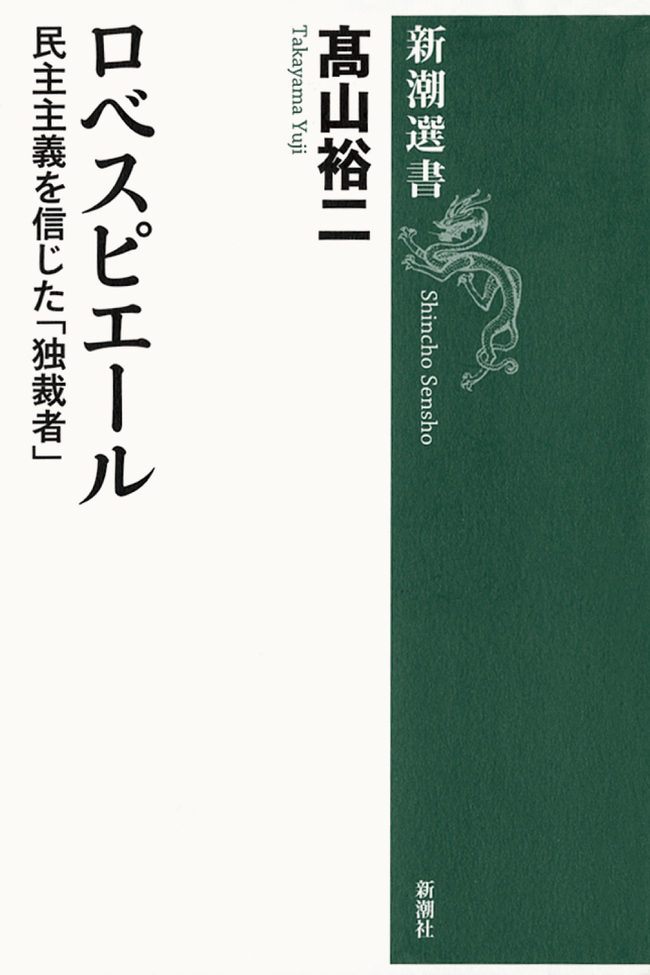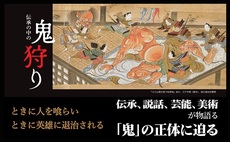ロベスピエールの理念に学ぶ
「政治家と国民」の関係性とは
フランス革命において、人民の圧倒的支持を背景に政敵を次々と粛清し、最後は自らも断頭台で葬られた、革命家であり、元祖ポピュリストのマクシミリアン・ロベスピエール。〝恐怖政治の独裁者〟というイメージは、今もなお、根強い。
だが、ロベスピエールは当時最も身分の低かった第三身分(平民)出身であり、「私は人民の一員である」と言い続けた勤勉実直な人物であったことが語られることは少ない。何より、民主主義を誰よりも信じていた。その彼の言動、政治思想などを丁寧に紐解いた作品が『ロベスピエール』(新潮選書)である。著者で明治大学政治経済学部准教授の髙山裕二氏は、執筆の動機をこう語る。
「ロベスピエール=恐怖政治と単純化されることが多い。だからこそ、彼のメッセージなどを通じて、生涯かけて探求した民主主義本来のあり方を考えてみたかった」
髙山氏の言う「民主主義本来のあり方」とはどういうものなのか。
「ロベスピエールが目指したことは、『代表者と人民の透明な関係性』であった。それは代表者が人民との信頼関係を構築することで、意思疎通できる関係性のことである。また、代表者も間違えることがある。だからこそ、人民の請願権や蜂起権を重視し、代表者を通じて、人民の主張や意見を議会に届けることを徹底させようとした」(同)
現代の日本の政治家と国民との間には見られない関係性である。
また、ロベスピエールは、常に「代表者の責任は重い」と指摘し、彼らに「美徳」を求めた。つまり、私益で政治を行うのではなく、公共の利益を徹底して追求するということだ。彼が「清廉の人」と呼ばれるゆえんである。清廉とはつまり、腐敗していないということだ。「彼は、エリートであると同時に、民衆側にも立つというスタンスを崩さなかった。つまり、双方の対立を『調停する』可能性を模索していた」(同)。
確かに、ロベスピエールは、腐敗している政敵を次々と処刑した人物で、彼の行為を手放しに称賛することはできない。だが、現代の政治家がロベスピエールのように清廉であるかといえば、必ずしもそうとは言えない。昨年の衆院選で自民党が大幅に議席を減らす原因にもなったいわゆる「裏金問題」はその典型だ。
ただ、そんなロベスピエールにも弱点があった。「自分こそが正しい」という考え方が支配的であったことだ。政治家としての〝余白〟や〝ユーモア〟が乏しかったのである。
「『自分たちこそ正義』という価値観が世の中を覆い始めると、逆に、それ以外の個人の自由が損なわれる。行き過ぎると、フランス革命のように苛烈な結果を招くこともある。清廉さや潔癖さが政治や社会をより良いものにするとは限らない。だが、現在の政治は、あまりにも透明さや真実さが失われつつある」

つまり透明性と余白という相容れないもののバランスが重要なのだ。
また、フランス革命は、『陰謀論の政治』の幕開けでもあった。メディアも発達し、人々は様々な発信を行い、大衆規模で陰謀論が広まった。
「代表者が民衆に選ばれるということは、絶対王政というアンシャン・レジーム(旧体制)の変更を意味する。それは、既存の制度や価値観が瓦解することを意味し、これまで正しいとされてきたものが正しくなくなり、『何が正しくて、何が正しくないのか』が分かりにくい状況となり、陰謀論が生まれやすい。皆が『これが正しい』と言い始めるからだ。それにより、フランス革命では多くの人々が犠牲になった」
このことは、SNS全盛の現代にも大きな示唆を与える。