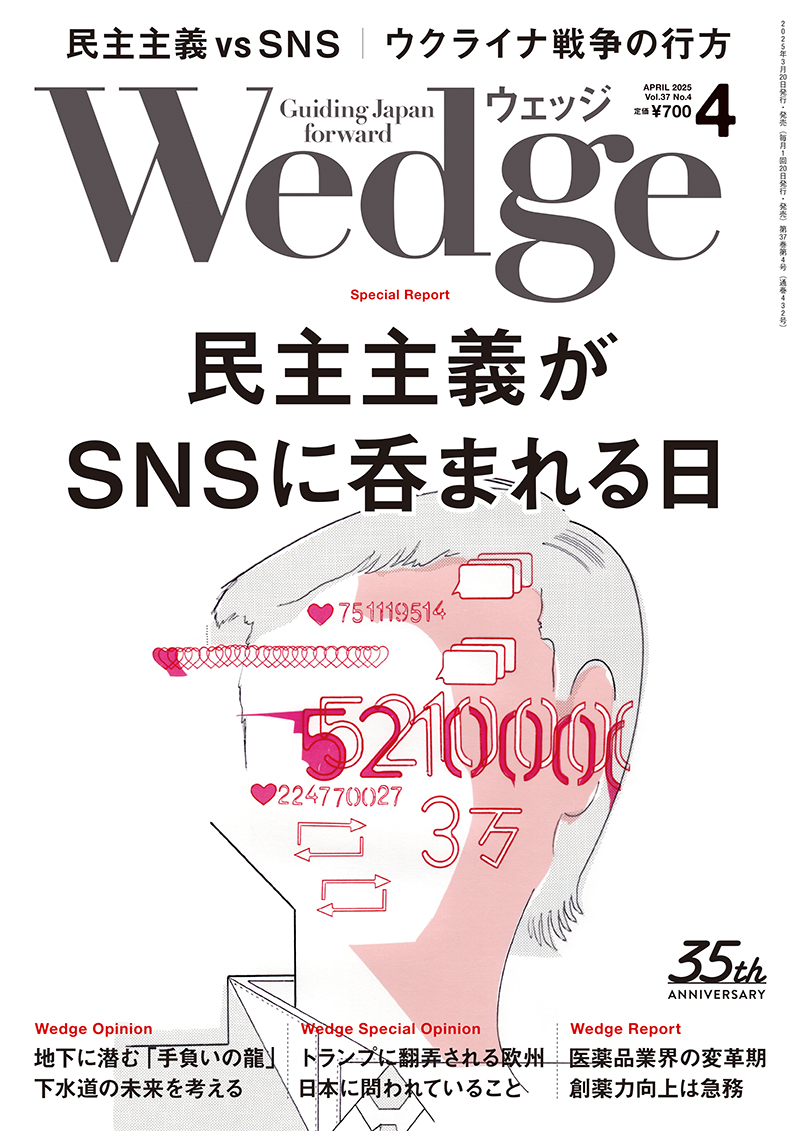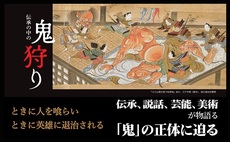「SNSが発達し、情報の個別化、断片化が進んでいる。また、『103万円の壁』など政策が極度にシングルイシュー化し、政治で取り組むべき全体像が見えにくい。様々な情報が飛び交う今だからこそ、複数のメディアを通じて多角的に情報を見る習慣を身につけていくこと、自分の関心外のことも学び、社会全体の流れを見ていくことが重要なのではないか」と髙山氏は指摘する。
日本社会に潜む課題と
〝天守閣〟の議論を
人間の「本質」や「特性」の問題に加え、もう一つ、日本社会に潜む特有の課題もおさえておかなければならない。前出の筒井氏は言う。
「歴史的に見て日本は、ヨーロッパとは異なり、平等主義的『大衆社会』の性格が強い。近代以降、日本のエリートは、相対的に中・下層階級出身者がなり易く、その人の出自や貧富の差にかかわらず、勉強による『教養』を身につければエリートになる可能性が高かった。
エリートは大衆から『尊敬に値する人』だと理解される一方で、大衆との距離が近くなりやすく、彼らの意見や世論に引っ張られ、必然的にポピュリズムに流されやすい。太平洋戦争も軍部独走で行われたという意見もあるが、『バスに乗り遅れるな』とばかりに熱狂した大衆を軍部・指導者が無視できなかった面もある。コロナ禍でもそうであったが、日本は下からの同調圧力が極めて強い社会であることに留意が必要だ」
大衆とエリートの距離が離れすぎれば全体主義のリスクが高まるが、日本の場合は、その逆なのである。平等主義的「大衆社会」の性格が強い分、我々は、こうした日本社会固有の課題、特徴を常に意識しておく必要がある。
現在、国内外を問わず、戦後秩序や既存の価値観が大きな変更を余儀なくされている。トランプ2.0はその象徴だ。日本は現在、主要7カ国(G7)の一員だが、グローバルサウスが台頭し、権威主義国家も勢いを増している。筒井氏は「G7の一員として民主主義などの価値を尊重することはもちろん大事で、その基礎づけを考えていかねばならないが、それはいわば共通の城壁である。今後、各国は城壁の中で何を守り、何を目指していくのかが問われることになる。日本はその〝天守閣〟とは何かを議論していく必要があるだろう」と指摘する。
あらゆるものは変化する。既存の秩序、体制、組織などに永遠はない。2月28日の「トランプ・ゼレンスキー会談」の決裂は、その予兆を感じさせる出来事でもあった。
日本も明治維新や昭和の敗戦で、社会は大きく変化したが、それら変革の担い手、原動力は紛れもなく人間であり、国論を二分する大きな議論や様々な試行錯誤もあった。
これからの日本に求められることは、変化を受容し、国民と国民、国民と政治家、与党と野党が、自由で開かれた対話のもと、ロベスピエールの言う「透明な関係性」を築くことだろう。当然、群衆同士の暴力では建設的な対話は生まれない。
我々は「大転換の時代」を生きている。日本の〝天守閣〟とは何か、その実現に向けどのような社会をつくっていくのか、それを支える人間はどうあるべきなのか──。今こそ、真剣な議論と対話が必要だ。