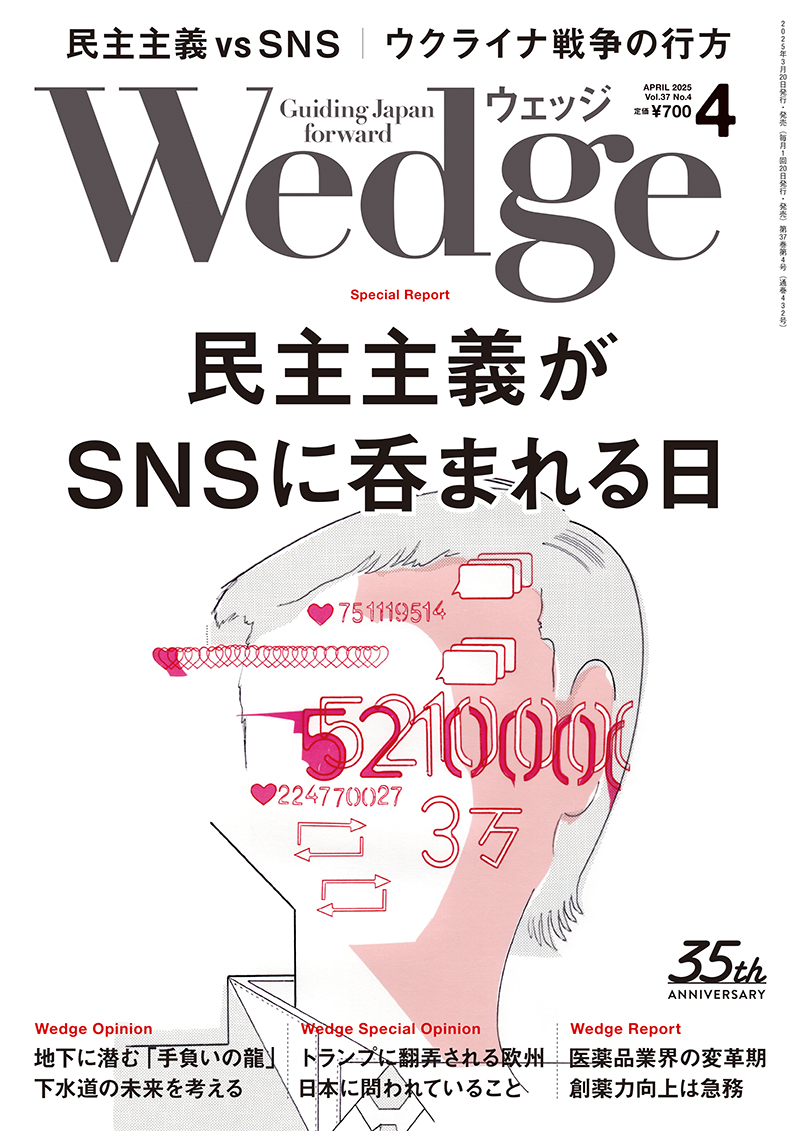打ち上げ頻度の向上に
立ちはだかる壁
各地で芽吹くこうした動きを止めないためには、民間任せにせず、国が前面に立つべき課題が二つある。
一つ目は漁業者との調整だ。ある関係者は「現行制度では打ち上げ時に警戒区域への進入を禁止したり退去を命じたりする法的根拠がなく、漁業関係者には協力を〝お願い〟して回るしかない。打ち上げの日程も建前上は観客が集まる休日としているが、本音では漁業者に配慮して、市場に影響しないように設定している」と実情を話す。実際、昨年3月9日には、スペースポート紀伊から「カイロス」初号機の打ち上げが予定されていたが、ロケット発射直前に警戒区域への船舶の侵入が発覚、打ち上げが延期となっている。
また、漁業関係者への「補償金」の負担も少なくない。漁業権に詳しい生態系総合研究所代表理事の小松正之氏は、「水産政策実施上では海は国民共有の財産であると認識されているが、法律上、漁業権は『物権』である。つまり、土地と同じ扱いで妨害行為排除権を有するため、実際に漁を行っていなくても、補償を受けられる。また、事前に受け取るため金額の根拠も曖昧だ。漁業補償は、米豪などのように営業補償とし、実害分を根拠立てて補償する形にしなければ、漁業者は過度に補償金に依存し、海を活用する新たな産業にとっても足枷になる」と指摘する。
もう一つは法律の整備だ。民間の宇宙港には、ロケットの打ち上げ以外にも、一般人が宇宙に行く「宇宙旅行」の需要を見込む場所もある。
「米国では有人飛行が実現しているが、日本の打ち上げに関する法律『宇宙活動法』の対象は無人ロケットや衛星であり『人』に関する記載がない」と前出の青木氏は指摘する。
加えて「有人飛行に関しては、まだ環境が整っていないという慎重な意見もあるが、有人飛行にチャレンジする国内企業も出てきている中、詳細がなくとも、拠り所となる〝一文〟があるかないかによって、国の本気度の伝わり方、そして企業が事業の技術開発のスピードも圧倒的に変わる」と法整備の意義を語る。
こうした他産業との調整や法整備は、民間や地方自治体が主導して行うには人材面でも資金力の面でも限界がある。国として宇宙という新たな分野での民間ビジネスを後押しするのであれば、土台となるスペースポート整備が日本の宇宙開発の駆動力となるよう、これまでの〝レガシー〟を突破する旗振り役こそ、政府に積極的に担ってほしい。