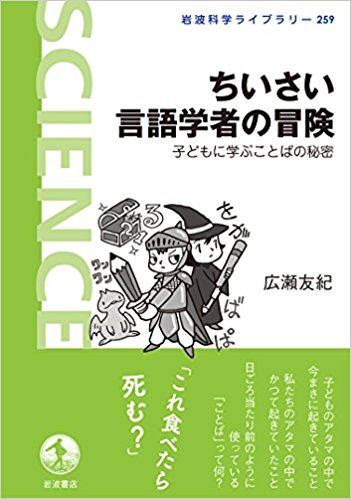――何の前提知識もなしに、まずは音を聞き分け、単語を聞き分けるとは実はすごいことが赤ちゃんの頭のなかでは行われているんですね。では、語の習得自体はどのように行われるのでしょう。
広瀬:大人になってから外国語を学ぶときは、知らない単語があれば辞書を引いて調べることができますが、幼い子どもが母語の単語を覚える過程とそれは根本的に異なりますよね。何しろ、新しい語らしきものを耳にしても、それがその場における状況や事物のどの側面を言っているのか、どういう意味の範囲をとっているのか、ということからして最初からはわからないのですから。たとえば、犬を表す「ワンワン」という単語を耳にしても、それが動いているもの全般を表す意味と捉えるかもしれませんし、動物全般のことを示しているとするのかもしれません。逆に、そのとき目の前にいるのが隣の家のペットだったら、その特定の犬を指す名称だという解釈をしてもおかしくないのです。
――それが「ワンワン=犬」と認識できるようになるのはどうしてでしょうか?
広瀬:ワンワンの例で言えば、4つ足で動く動物をワンワンと言うようになった赤ちゃんは、猫や牛、馬のどれを見てもワンワンと言うようなことがあります。これを言語学では「過剰拡張」と言います。過剰拡張方向の間違いは端から見て気づきやすいので、話題になりやすいです。逆に「過剰縮小」というタイプもあり、例えば隣のポチ限定で「ワンワン」という語を解釈する場合がこれにあたりますが、端からみて間違った範囲で解釈していることがわかりにくいので観察・報告されにくいケースです。拙著(以下『ちいさい言語学者の冒険』)ではこの「過剰縮小」が極めてドラマチックに観察された例を挙げていますのでぜひ読んで笑ってください。
最初はこのように、ことばの意味範囲より「広すぎる」または「狭すぎる」解釈から始まったとしても、子どもたちはやがてさまざまな事例にふれながら意味範囲の修正を行い、次第に正しい意味範囲・解釈に近づけていくようになります。周囲の大人たちのやりとりも含めた外界を通して入ってくる情報を一方的に覚えるだけではなく、すでに頭のなかにある知識との微調整により語彙の知識を整備してゆくのです。
――じゃあ電車を指して「ワンワン」でもそんなに心配しなくてよい、と。では単語がわかるようになった次はどんな段階に入るのでしょうか?
広瀬:文単位で言葉を理解するには、語と語をつなげる統語レベルの決まりがわかっている必要があります。文法規則についても、子どもは教科書や文法書で教えられるワケはありませんので、自力で試行錯誤を繰り返して大人と同じ規則を身につけていきます。この過程で「過剰に一般化された規則の姿」が見られます。動詞や助動詞の活用はまさにそのお宝箱。
「これたべたら死む?」
「お兄ちゃんこた(来た)よ」
「ガチャガチャすれる?(することができる?)」
「靴はきさせて(はかせて)」
「死む・死まない・死めば」などの間違ったナ行の活用は、「読んじゃった<読む・噛んじゃった<噛む」という、数のうえでは圧倒的に多いマ行動詞の活用形から類推して一般化してしまった(「死んじゃった<死む」)結果だと『ちいさい言語学者の冒険』では紹介していますが他の例も似たような過程で発生した類推の産物です。過剰一般化された規則から生み出される形は、表面上は子どもの『間違い』です。ですが、この「過剰一般化がみられる」ことこそが、子どもが順調に言語の規則を習得しつつあることの証拠なのです。大人の丸覚えコピーでこのような例が発生するわけがないのですから。