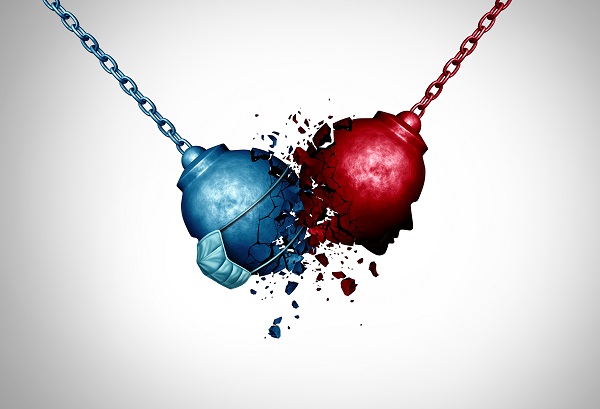
NHKスペシャル「パンデミック 激動の世界」(8月29日・30日)の「ウイルス襲来 瀬戸際の132日・前後編」は、日本で新型コロナウイルスの初めての感染者がでてから、緊急事態宣言が全面解除された5月25日までの132日間の真相を探ったドキュメンタリーの力作である。
番組を進行する、大越健介キャスターが見るものに語り掛けるように、感染を防ぎながら経済を回すという難題は解決されていない。「科学の知見と政治家の発信力」がともに必要であることを改めて認識させる。
中国・武漢からの帰国者の検体が、国立感染症研究所に搬入されたのは、1月14日のことである。翌日に検体から陽性反応が出た。松山州徳室長は当時を振り返って「まだ制御できると思った」という。
加藤勝信・厚生労働大臣もまた「(新型コロナウイルスが)入ってきたなという感じだった。情報収集には当たっていた」という。
日本を代表する感染症の専門家たちは、重大な危機感を抱いていた。それは、11年前の新型インフルエンザを受けて、翌年に政府とともに策定した感染症対策がほとんど手つかずのまま先送りにしてきた苦い記憶を伴っていた。新型コロナウイルス対策をめぐって、各界から指摘されたさまざまな体制づくりが盛り込まれていた。
感染症対策の意思決定プロセスの責任体制の確立であり、さまざまな財政支援であり、保健所の強化、PCR検査の拡充などである。
専門家会議の副座長を務めた、尾身茂氏は「日本は、台湾と異なってSARSに見舞われなかった。また、韓国と違ってMARSに遭遇しなかった。その間に地震や津波の災害にあって、感染症に対する10年前の提言が共有化されなかった」と、悔やむ。
厚生労働省健康局の正林督章局長は「SARSもMARSも被害がなく(政府のなかで感染症対策が)イメージできなかった。財政当局が予算をつけづらかった面がある」と、語る。
番組は、日本が新型コロナウイルスの感染者と死亡者において、先進国のなかで比較的軽微に済んだ事実を踏まえて、「第1波はぎりぎり制御した」、それは「貧者の戦い」だった、と指摘している。
10年前に提言された、感染症対策の強化がないままに、専門家会議は世界で初めてといっていい「三密(密閉空間、密集空間、密接場面)」を避けるという戦略を見出し、感染者とクラスターを追いかけて、隔離する戦術でコロナという敵に向かったのである。

















