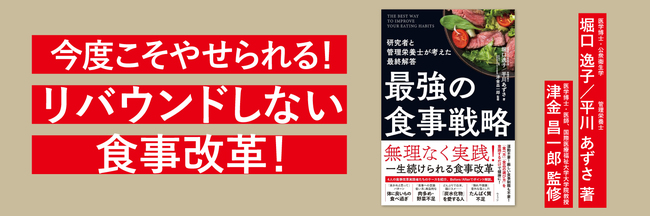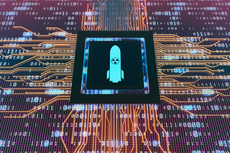筆者(堀口)は、たまたま両足を骨折し、入院生活を送った3カ月間、栄養のバランスとエネルギー量(カロリー)が管理された食事をとり、3食しっかり食べていたにもかかわらず自然と痩せていった。この食事を普段の食生活で再現しようと、管理栄養士の平川さんに相談したことから、この「食事戦略」が生み出された。
本コラムではその考え方や実践法を紹介していく。
*本記事は『最強の食事戦略』(堀口逸子 平川あずさ、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
目に見えないカロリー
見えている食品・食材
食事を選ぶとき、献立やメニューを眺める。同じメニューでも例えば、スパゲティミートソースも、当然のことながら店舗によって具材や全体の量、また作り方が異なっている。メニューにカロリー(以下、エネルギー量)が表記されている場合もある。エネルギー量を見て少ないものを選ぼうと考えることもあるだろう。その1食のエネルギー量を減らすだけでよいのか、どのくらい減らさなければならないのか、分かって食べているだろうか。
1日の食事おのおのすべてのエネルギー量が分かることはほとんどない。栄養士が計算してくれていてこそ分かるのがエネルギー量。残念ながら毎食栄養士のお世話になることは、病院に入院しない限りない。
エネルギー量は目に見えない。見えないものを基準に考えられるのか。私たちに見えているのは、食品や食材。ならば食品や食材を基に日常「分かる」もので考えるべきである。
目の前の「1食」ではなく
「1日」単位で考える
会社でのランチタイム。今日は何を食べよう、今日のお弁当のおかずは何だろうなど、あなたは食事前に何を考えているだろうか。栄養のバランスだろうか。昨日食べた食事だろうか。夜の会食の食事を考えているのだろうか。私たちは、その1食で何を食べたいかを考えて、買い物をしたり、食事をしたりしている。
しかし、実は栄養士の頭の中では同時に「1日の食事」を考えている。さらに、その1日を7日分、すなわち1週間の献立として、魚・肉・大豆・大豆製品が重ならないように、同じ味付けが続かないように、そして野菜の種類も少しずつ変えたりして、工夫する。1カ月で、より多様な食品を取れるように、すなわちいろいろな栄養成分が補えるようにと考えている。
食事バランスガイドを見ても「1日の食事」で成り立っている。すなわち1食ではなく、1日単位で食事を考えなければ健康を目指す食事にならないということである。そういえば野菜についても、健康日本21の目標として、1食ではなく「1日」350gとなっている。