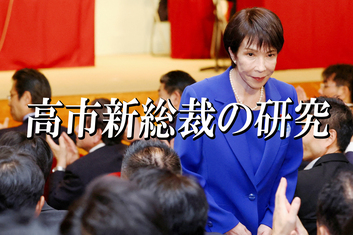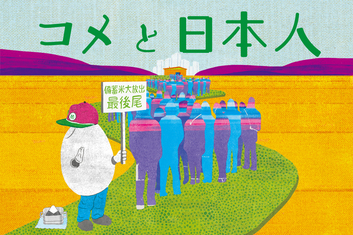認知症患者数推計の出所を探して
5月8日のニュースは、「認知症の患者数が2030年に523万人にのぼる見通しとなった」(日本経済新聞)、「認知症の高齢者は団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年に推計584万2000人」(NHK)などと報道されたので、多くの人にとって記憶に新しいことだろう。
ただ、この種の健康問題に関連する報道に対して、私はついつい「批判的吟味」をしてしまう。「この報道の元になるエビデンスはいつ、誰が、何を(誰を)対象に、どのように生み出され、どこで発表されたのだろう」「それはプライマリ・ヘルス・ケアの現場で意味のあるエビデンスだろうか」などの疑問が自動的に湧いてくる。家庭医の職業病とも言えて、家族の失笑を買っている。
今回のエビデンスの元は、厚生労働研究班(代表者・二宮利治九州大学教授)が5月8日に発表した推計であることは報道された記事に書かれていた。ただ、厚生労働省のウェブサイトを検索しても、容易に推計の元となった最新の情報を見出すことはできなかった。しばしば思うことであるが、日本のメディアも省庁も、報道に関連する情報源(参考文献やウェブサイト)をもっと参照しやすく明示してほしいものだ。
幸い、頼りになる知人から、内閣官房の第2回「認知症施策推進関係者会議」で発表された資料があると教えてもらえた。
それによると、今回発表されたエビデンスは、2022〜23年度に石川、島根、愛媛、福岡県の4つの町で行われた高齢者の認知症および軽度認知障害(mild cognitive impairment; MCI)の有病率を調べる悉皆(しっかい)調査(調査対象となる母集団すべてを調べる統計調査。全数調査とも呼ばれる)を元に推計したものだった。
認知機能の検査方法
この調査では、一次調査のスクリーニングとして調査対象者のほぼ全員にMMSE(Mini-Mental State Examination)という、有効性が検証された方法を用いていた。MMSEは複数の質問や指示への反応を点数化して合計する検査で、1975年に公表されて以来世界中で使用されてきた認知機能スクリーニングの標準的検査である。私もカナダで専門研修していた90年代には何度も使用した。
日本では、改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R)が認知機能の検査により使われている。HDS-Rが記憶力に重点が置かれているのに対し、MMSEでは言語能力や視空間認知能力も評価できる。
ただ、2011年に発表された米国の医学雑誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン(NEJM)』の論考によると、2000年ごろからMMSEの考案者らが著作権を主張して、MMSEの使用にはライセンス料(1検査あたり1.23米ドル)がかかるようになり、MMSEが公の場からは姿を消しつつあるようだ。現在はどうなっているのだろう。
著作権保護と科学的知見の公共性とのバランスは難しい。日本の診療ガイドラインの閉鎖性にはしばしば辟易するが、これも類似の問題である。