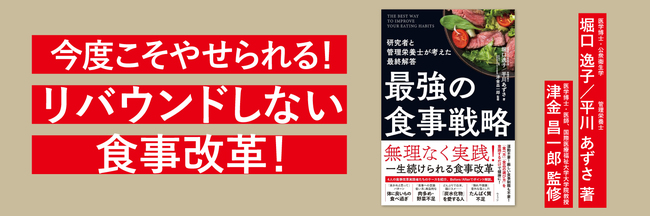このコラム『研究者と管理栄養士が考えた「最強の食事戦略」』を読んでくれている人は、自分の食事や健康管理、ダイエットに関心があると思われる。生活スタイルは一人一人異なり、食事のスタイル(自炊メインか、誰が食事を用意しているか、外食の回数等々……)もさまざまであろう。それは問題ではない。大切なのは「食事の選択ができるかどうか」である。
*本記事は『最強の食事戦略』(堀口逸子 平川あずさ、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
*本記事は『最強の食事戦略』(堀口逸子 平川あずさ、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
自炊にこだわるよりも食事の「選択」ができるかどうか
健康づくりにおける主な取り組みは、運動と食事。健康管理のための運動は、トレーナーのサポートがつくことはあっても、自分の体を自分で動かすしかない。ところが、食事については必ずしも自分だけで、ではない。
筆者(堀口)が骨折で入院している間、病院では栄養のバランスがとれた食事が提供されたが、病院から一歩外に出たらそうはいかない。そのため、外食にしても1人、複数人の場合と、その都度その食事の役割、目標を考えるようになった。1人で外食するには、いろいろな食材を食べ、またたんぱく質を食べる機会と捉え、ジャンルを考える。そして、量をイメージしてお店を選択。人数が多く鍋料理の場合は、野菜を食べる機会と考えたりする。その野菜の量も、100g以上を量って1人で鍋をして初めて分かった。以前は食べ過ぎていた。
食事を考えるときの基本単位は「1日」である(第1回目記事「<研究者と管理栄養士が考えた食事戦略>カロリーは目に見えないから、食べる「量」で食事改革」参照)。その1日の食事すべてを自分で考え準備できるなら、当然、栄養バランスのとれた食生活への転換ははかりやすく、かつ維持しやすい。自炊かどうかが重要なのではなく、自身の食事を自分で選択できるのか、あるいは、提供された食事の目標が何かを考えられるか、なのだ。外食・中食という枠で考えるべきでない。