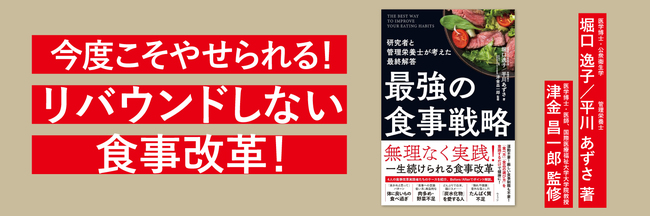確かにこの1食=1回の食事で栄養や新・3色食品群(第1回目参照)を満遍なく取ることを期待するのは難しい。それならば、割り切って何かに「集中」するのがよい。大切なのは外食・中食の「メリット」=「日常利用していない食材」や「調理できない食事」を食べられること、を最大限享受することである。
*本記事は『最強の食事戦略』(堀口逸子 平川あずさ、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
外食・中食で同じものを
食べ続けては台無し
外食・中食の1回分で新・3色食品群のすべてをそろえるのが難しくとも、メリットはある。それは、日常利用していない食材や、調理できない食事を食べられること。私たちが健康的な体をつくるためには、さまざまな栄養素が必要である。食材おのおのに、さまざまな栄養素が含まれているが、私たちは、食材一つ一つに含まれている栄養成分が何か、確認することはしないし、知らない、または覚えていない。まして栄養成分の量をコントロールするのは至難の技である。栄養成分を計算によって日常管理しているのは、栄養士が対応している病者の食事だ。
私たちの食事では「さまざまな食材を摂取することが、さまざまな栄養素を摂取することにつながる」と考える。家庭で調理した食事は手に入れられる食材と身に付けている調理技術に限界があり、また調理をする人の食材の好き嫌いにも影響を受ける。そのため、さまざまな栄養を満遍なく摂取するための外食・中食なのである。同じものばかり食べていては、そのメリットを否定してしまう。すなわち外食・中食では、同じものを食べないことが健康につながるということである。
移動時間の食事は
立ち食いそばよりコンビニで
私(堀口)は、東京で働き始めてからは、昼食時間が移動時間になり、電車で近郊を移動し、昼食が十分に取れない場合がある。おなかがすいていないのに早めのお昼を食べれば、夕飯までにおなかがもたない。昼食を抜いても同じである。短時間で立ち食いそばをかき込むこともあったが、満足感は得られにくい。
この場合、新・3色食品群すべてを取ろうとせず、何かに集中する。コンビニエンスストアのイートインコーナーを利用して、果物とヨーグルトで済ませたり、車中で、たんぱく質が具材となっているおにぎりやサンドイッチを食べたり。これらは、長時間の空腹を避けるための食事と捉える。