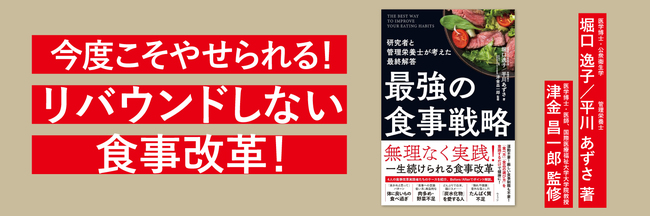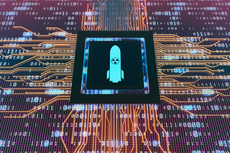*本記事は『最強の食事戦略』(堀口逸子 平川あずさ、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
「食品の見た目」や「誰と食べるか」……
摂取量には「満腹感」以外も影響する
摂取量は、私たちの感覚(満腹感)や食べ方以外からも影響を受けていることが、心理学や認知科学の研究から明らかとなっている。それは大きく「食品周辺環境」と「食環境」に分かれる。
「食品周辺環境」は、器の大きさ、食品のポーションサイズ、パッケージの大きさ、食品の見た目、同時に提供される食品の味や見た目のバリエーション、食品の存在が意識に上がりやすくなることなどである。
「食環境」は、雰囲気、照明、音(騒音、音楽)、誰と食べるかなどである。私たちの体に食事量をコントロールする能力が備わっていないのだから、これらを積極的に上手に利用していきたい。
食環境では、気温の低いところでは、高い環境下に比べてより多くの量を食べるようになることや、明るい照明の場所よりも、ろうそくなどの暖色で暗い照明の場所の方が、食事量が多くなることが分かっている。自宅では、快適な室温で、明るい照明のもとで食事をしよう。誰と食べるかは、他者がどの程度の量を食べるかを観察することが満腹感の見積もりにつながっていると考えられており、親密な関係の相手、見ず知らずの相手との食事の場合に、摂取量が多くなることが知られている。
量を把握するためのスケールとして飯わんについて説明した。その器が摂取量に影響を与えるのだから、器の大きさを考えなければならないということである。それは、小さめの器を使うこと。当たり前のことだが、小さい器に大量に盛り付けることはできない。
飯わんであれば、一般的には男性用といわれている4寸(直径約12cm)でなく3.8寸(直径約11.5㎝)を推奨する。私(堀口)は、この食べ方を身に付けてから、使用していた器のサイズがかなり小さくなった。飯わんも、子供用のサイズである。糖尿病の人が、小さい器を探すと子供用のものしかないとのことで、大人が使う子供用サイズの器を作るメーカーも最近は散見される。