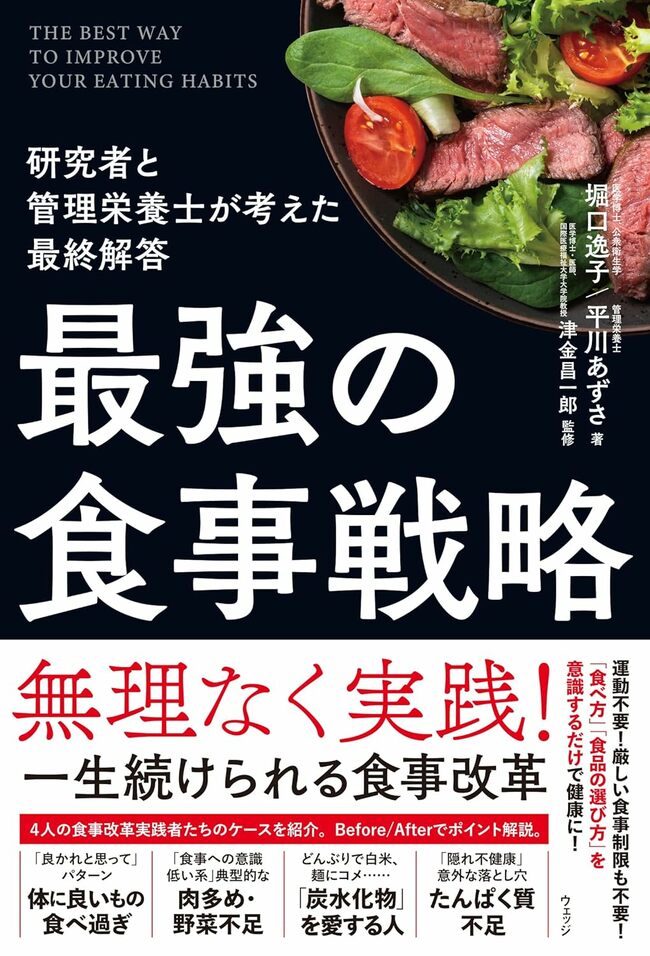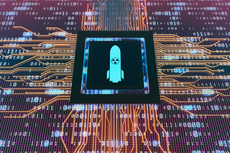また丼も、小丼にすれば、うどん半玉でも麺が少ないなどとは思えない量になる。ラーメン丼もサイズがいろいろある。実家にあった昔の丼を使うようになったら、市販のインスタントラーメン(袋麺)ではあふれてしまうことが分かった。ロングセラーを続ける袋麺の麺量はいかに少ないかも確認して分かった。先述した、満腹感は「山盛り盛られている」という見た目にも影響されることからも、小さい器の使用をおすすめする。そしてそれにある程度の重さがあることだ。
パッケージやポーションサイズが大きい食品を、残すことなくそのまますべて食べてしまえば当然摂取量は多くなる。適切量が入ったパッケージやポーションサイズの食品が好ましいということである。ごはんをどれだけ飯わんによそうか、ごはんの量ではなく飯わんが基準になっていないか。食事を器やパッケージに合わせるのではなく、適切な量に、器を合わせていくことなのだ。中食で調理済み食品を購入する際には、「山盛り」に見せる小さめの器を購入し、量を確定させ、それを器に盛り付け、満腹感を高める。
同時に提供される食品の味や見た目のバリエーションが多様であるほど、その摂取量が増加する。これは主菜・副菜といった皿数以上の話である。例として、味の違う食品を食べ比べと称してそろえたり、キャンディーの色違いがあったりすると、より多く食べてしまう。また透明のビンに入れておくなど目につき、食品の存在が意識に上がりやすくなることも、より多く食べてしまうことにつながる。ならば、おやつは、見えないところに隠しておこう。
「満足感」を高めれば
ダイエット効果も高まる
量が多ければ、一般的に「満腹感」が得られる。「満腹感」が得られたら「満足感」につながる。それでは、食事から「満足感」が得られたら「満腹感」や「食欲抑制」につながるのか。
研究論文では「満腹感」と「満足感」の関連を示唆する記述が見られるが、「満足感」は食物摂取後に得られる感覚で、ご褒美や喜び、いわゆる幸福感なども含まれ、それを確定することなど評価については研究途上であった。そして、食物摂取後の感覚の重要性や長期的な摂取の予測についてはほとんど研究されていない。「満足感」は摂食後に限らないため、今後の研究に期待する。高たんぱく食に関した研究において、食事の処方を守ることを含む「満足度」が高く「空腹感」が少ないほど体重減少が大きかったとする報告がある。すなわちダイエットでは、コントロールを怠らず「満足感」を高め、「空腹感」を避けることによって効果を高められると考えられる。「満足感」も重要な要素の1つなのである。