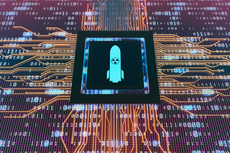突発的な欠勤者の発生に備え、通常であれば事務所に助手が控えているが、この4月には社長の甲斐さん自ら15年ぶりにごみ収集車を運転し、収集して回る機会もあったという。
「仮に数人が入社しても、半年後には半数以下です。入社後3日で来なくなったことさえありましたよ」(同)
同社は少しでも会社・業界のイメージを変えようと、車体はあえて汚れが目立つ黄色に、ユニホームはオレンジ色に統一し、常に綺麗な状態を保つことを心掛けている。
横浜市資源循環局業務課課長の澤田亮仁さんは、「人手不足のあおりを受ける業界であり、若い世代のための環境改善は官民の区別なく大きな課題です」と述べる。一方で、「確かに『週6回』という仕事量は入札の時点で決められています。しかし、収集日を少なくするなど、ごみ収集員の方々の働く環境を見直せば、市民生活などにも大きな影響があります。市民からの十分な理解を得る必要もあり、その決断は慎重にならざるを得ません」と、苦しい胸の内を明かした。
収集されたごみが向かう先は
「夜も眠らぬ」焼却工場
1960年代、高度経済成長とともにごみの量は一気に増加した。
当時、東京都ではごみの多くを焼却することなくそのまま埋め立てていたが、埋め立て地の残量にも限界が見え、ごみを焼却処理するための清掃工場を23区の各区に整備する計画が進められた。
66年11月、杉並区高井戸に清掃工場を建設することを発表したが、住民に対する事前の説明もない一方的な通知だったことから、杉並区民は猛反発。当時の東京都知事である美濃部亮吉が「東京ごみ戦争」を宣言し、杉並区民と東京都との約9年にわたる争いがあった。
大きな社会問題となった東京ごみ戦争は、一国民としてごみと社会に向き合うことの大切さを示したとともに、その後70~80年代にかけて全国に焼却工場を整備していく上での一つの契機にもなった。
横浜市の金沢工場には、1日400㌧のごみを燃やせる焼却炉が3基ある。1日に1000㌧を超えるごみが搬入される日も少なくないというが、ごみを焼却炉に投下する作業も、それを燃やす作業も、24時間体制で行っている。
焼却前のごみを溜めるピットの深さは、10階建てのビルと同程度。資格を持ったオペレーターがクレーンを操作し、溜まったごみを焼却炉へ投下していく。操作室ではピットを一望できるよう壁一面が窓仕様になっているが、反射を避けるために部屋の照明を全て消しており、暗闇の中で業務にあたっていた。
いかにごみを焼却し続けるか。その導入となるのは、炉自体を約900度にまで熱することだ。そこへごみを投入し、自然発火させる。その後は燃料であるごみを入れ続けることで火を保つという。「原理はバーベキューに似ているかもしれませんね」と易しく解説してくれたのは、技術管理係の守屋翼さん。工場が24時間稼働し続けるのは、主に次のような理由からだという。
毎度火を絶やし、炉の加熱操作を繰り返すという運転方法ではエネルギーを余分に消費するため、コストもかさむ。その上、ダイオキシンなどの発生量を抑えるためにも高温での連続運転が推奨されている。
また、金沢工場では焼却時の熱を利用して蒸気を作り、タービン発電機で発電している。1日で36万㌔ワットアワー(kWh)もの発電量があり、その電気を工場内で使用するとともに、近隣の施設にも供給する。さらに余った電力を電力会社に販売することで、年間約10億円を売り上げており、市政にとっての貴重な財源としても活用しているのだ。
これらの事情を総合的に考慮し、24時間体制を維持している。