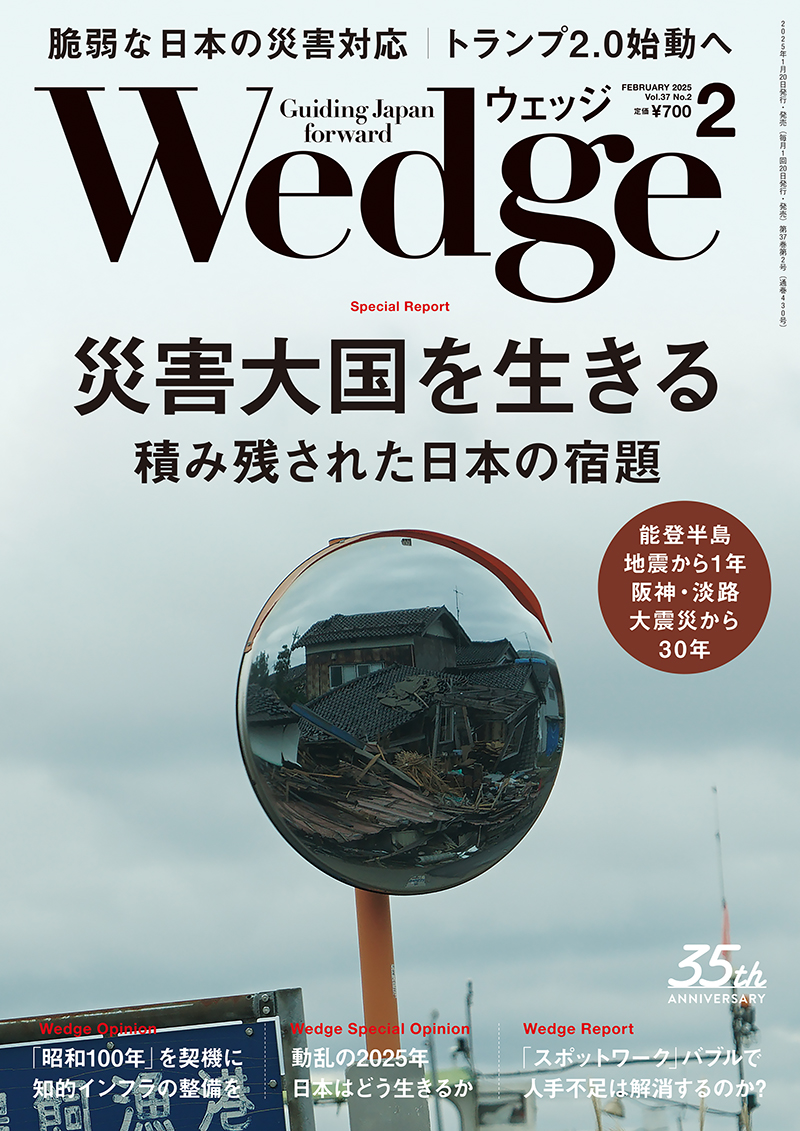防災基本計画では、基礎自治体ごとに食料や飲料水などの必要な物資の備蓄に努めるように記載されている。輪島市は、震度6強を記録した2007年の能登半島地震での経験をベースに、「2000人が被災する」ことを想定した防災計画を策定し、指定避難所の選定や物資の備蓄を行ってきた。しかし、昨年の地震では約1万3600人が避難所に入り、在宅避難や車中避難を含めると2万人を超える市民が被災した。前出の山本氏は「想定が甘かったことは反省しなければいけません。ただ、市民全員分の物資を備蓄することは現実的には難しい」と話す。
自治体間で防災意識や財政余力には大きな差があり、〝備蓄格差〟が生まれているという。冒頭の榛沢氏は「政府は基礎自治体が備蓄物資を購入する際の補助金の導入を検討していますが、補助金では一定額は自治体が負担することになり、財政余力に乏しい小規模な自治体ほど手を出さなくなります。やはり、国が一定の物量を備蓄しておくのが合理的」だと指摘する。
国も対策に動いている。内閣府は24年度の補正予算でプッシュ型支援に13.6億円を計上し、新たに全国7カ所に国による備蓄拠点を新設し、段ボールベッドなどを備蓄する計画を立てた。プッシュ型支援とは、食料、毛布、乳児・小児用おむつなどの8品目の他、必要不可欠と見込まれるものを国が調達し、被災自治体の要請を待たずに都道府県の備蓄拠点に搬送する仕組みである。
防災科学技術研究所特別研究員の宇田川真之氏は、「国による備蓄が充実すること自体は歓迎すべき」とする一方、「最後は市町村、ひいては、避難所や在宅などの被災者の手元に届くことが必要です。ただ、救援物資業務は、自治体に類似する平常業務がないため、混乱が生じがちです。それは、これまでも繰り返されてきた課題です」と指摘する。
輪島市門前総合支所地域振興課課長補佐の野中淳也氏は「昨年の災害後も、ペットボトルの飲料水を何百箱と送ってもらいましたが、避難所で荷物を下ろす人手も、保管しておくスペースもなく、キャパオーバーでした」と打ち明ける。また、物資要請の連絡がうまくいかず、人口が4800人、避難者が2500人の門前地区に、期限切れ間近のおにぎりが2万個届いたこともあった。
前出の浦野氏は、「ベッドも食事もトイレも、現場に送るだけではうまくいきません。それを運用するには『人』の力が必要だからです。しかし、自治体職員だけではマンパワーが不足します。だからこそ、民間のノウハウが不可欠です。同時に、平時より、防災意識の高い市民を育成し、有事の際に協働することも重要です」と話す。
支援団体の経験値と共に
根本的な法制度の改善を
「被災者が被災者を支える」構造を見直していく上では、NPOやボランティアのスキルアップも重要だ。被災者支援を得意とするNPO法人YNF(福岡市)代表の江﨑太郎氏は、支援団体が実践の経験を積む機会を増やすべきだと主張する。
「大きな災害ばかりに支援が集中していますが、竜巻や洪水など、比較的規模が小さな災害はたびたび発生しています。しかし、公的な資金援助がないため、多くの支援団体は局所災害まで手が回っていません。例えば、発災時には災害支援を専門とする民間団体に支援を発注するという意識を根付かせ、そこに公費を投じるという形に少しずつ変わっていけば、支援団体の経験値や対応力も向上し、自治体の職員の負担も軽減できるはずです」
榛沢氏も次のように話す。
「プッシュ型支援の充実や避難所の環境改善に向けた指針の改定も重要です。NPOやボランティアの育成も必要でしょう。しかし、基礎自治体任せの災害法制を改革しなければ、避難所の本質は変わらないでしょう。政府は、国民の生命と財産を守るという意識で、災害法制の見直しに着手しなければいけません」