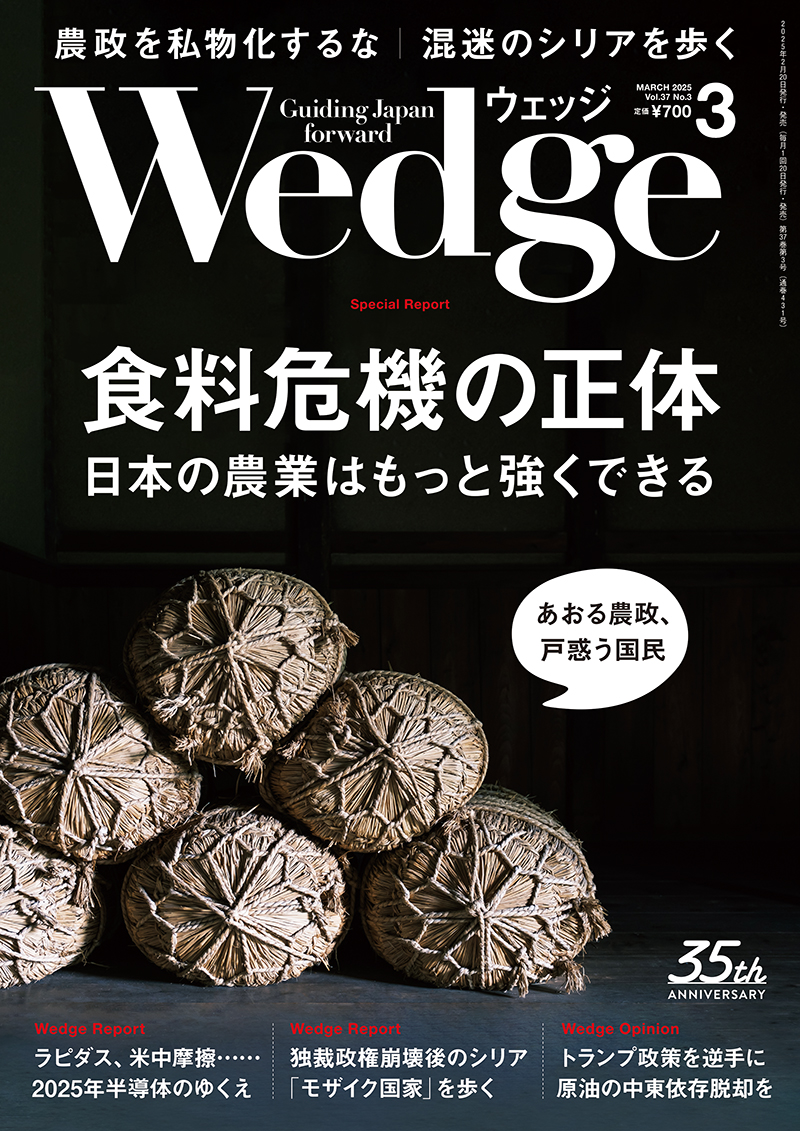休養の地から
内政外交の拠点へ
荻窪駅から南に10分ほど歩くと、高い建物のない閑静な一帯に至る。大正から昭和にかけて要人たちが邸宅を設けたこの地に近衛が安息の場所を求めたのは、最初の組閣から間もなくだった。日本初の建築史家である伊東忠太が設計した和洋折衷建築を医師の入澤達吉から譲り受け、西園寺公望の命名墨書を得て「荻外荘」と掲げた。広大な庭には芝生が敷き詰められ、四阿の他、ゴルフのグリーンとバンカーがあった。芝生の先は広い池。いまは一面の芝生と、樹齢数百年は超えようかという巨大なクスノキなどが残される。
車寄せから当時の玄関を入ると、正面が中国風意匠の応接室となっている。邸内はゆったりした中廊下が通され、南側に主人と家族のための部屋が集められている。昭和史を決する重大な話し合いがもたれたのは、広縁が回され、運転手や秘書らの控室が併設された客間であった。

広さ30平米ほどの洋室は、40(昭和15)年の「荻窪会談」を報じる朝日新聞の写真をもとに忠実に再現されている。内装は伊東のアジア趣味が感じられ、壁に掛けられた亀とニシキエビの細工物が目をひく他は、全体に落ち着いた設えだ。だが、写真に残る光景を仔細に眺めてみると、様々な想像をかき立てられる。
紺色の西陣織が掛けられた丸テーブルを4つのソファが囲んでいる。軍服姿の2人がソファに反り返り、奥には国際連盟脱退をしでかした外相が白い夏服で深々と腰かけている。残る近衛はというと、和服で浅く腰かける姿からは、強面の3人に気圧されるような様子がうかがえるのは気のせいか(この頃、近衛は痔疾に苦しんでいたとの証言もあるが)。卓上には銘々のメモ帳のほか、盛夏の季節柄、団扇が置かれている。
欧州ではドイツが破竹の進撃を続け、軍人からはさぞ威勢のいい言葉が飛び出したろう。だが、彼我の戦力の差を知る近衛であるなら、長く武門とわたり合ってきた家柄こそのしたたかな戦術、弁舌はもてなかったのか。岐路に立つ国家の行く末を案じて身命を賭す勇気はなかったのか。その後の歴史を知る我々は、ただ、無念の思いで胸がふさがる。これから1年と少し、近衛は先の迷言を発して辞任、東條内閣が成立して日本は真珠湾攻撃に突入する。
次第に戦況が悪化する中、近衛は吉田茂らと水面下で終戦工作を進め、戦後はいち早く連合国軍総司令部(GHQ)と接触し、マッカーサーから憲法改正の内意を受ける。新しい時代を主導する意欲を示す一方で、内外から戦争責任を問う声が上がる。日中戦争の責任は自覚した近衛だが、第二次大戦に呵責の念はなかったとされる。しかし、次第に米国の論調が厳しいものとなり、終戦の年の12月、GHQから近衛の逮捕が指令される。巣鴨プリズンへの出頭期限となっていた同月16日の未明、近衛は荻外荘で服毒して果てた。
自裁した12畳の書斎は当時のままである。洋室だったものを近衛が数寄屋風に改築し、天井や床柱には凝った設えも見せる。中央には大きな座卓が置かれ、部屋の隅には当時の屏風も復原されている。GHQの検視写真では枕元に逆さ屏風にして置かれていたものだ。
壁をくり抜いて仏壇を設けているのが筆者の目を引いた。直系に信長や秀吉と渡り合った近衛前久の名もある名家中の名家を、わずか13歳で引き継いだ。死の間際、先祖の位牌に何を語ったろうかと思い巡らし、粛然とした。