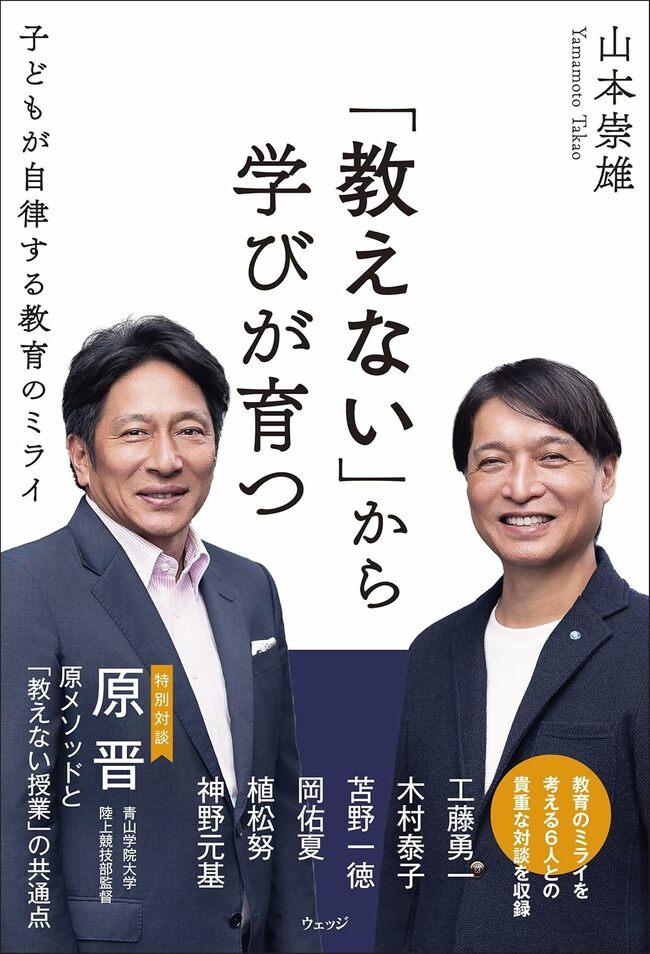「子どもを理解する」という教師の傲慢さ
木村:その先生とは普段の授業などでの接点はなく、あの日のたった数分の関わりだけでした。でも先生が教えてくれたことは後の私の人生を大きく変えたんです。中学校に進んだ私は、なんと水泳部に入ることになって。
山本:あれほど水が苦手だったのに水泳部へ?
木村:面白いでしょう。私は先生が教えてくれた「顔をつけない泳ぎ方」を知っているから、中学校に入ってからはプールが怖くなくなったんです。私のスタイルは、常に上を向いて進む背泳ぎでした。これなら水に顔をつけなくていいから(笑)。当時はスイミングスクールなどなく、子どもたちはクロールと平泳ぎしか知りません。そんな中で背泳ぎをしている私を見て、水泳部の顧問の先生が「すごい子がいる!」と興奮して声をかけてきたんですよ。
山本:まさかの熱烈スカウトが待っていたんですね(笑)。
木村:私は驚きましたが、あれよあれよという間に水泳部に入ることになって、中学校2年の時には近畿地区の大会に出場するまでになりました。大の苦手だった水泳が、その後は私の得意分野になってしまったんですよね。最終的に大学時代には水泳で全国6位まで進みました。すべてのきっかけはあの先生だったんです。
山本:教員の関わり方一つで、子どもの人生にここまで大きな影響を与えるんですね。改めて身の引き締まる思いがします。考えてみれば、教員は子どもの光っている部分にはよく注目しますが、陰になっている部分にはあまり目を向けられていないのかもしれません。
木村:そう、子どもの見えやすい部分は誰にでも分かるでしょう。私で言えば運動が得意だったから、その部分はどの先生も理解していたはず。でも水が怖くて仕方がない私のことはなかなか理解してもらえませんでした。これまでの日本の学校教育において、教員には子どもを理解することが求められてきましたよね。でも、「子どもを理解する」って本当にできるでしょうか。私自身には2人の娘がいますが、正直に言って娘たちのことも完全には理解できていませんよ。他人の子どものことまで100パーセント理解できる教員がいるとしたら、それは神か仏の領域に達しているのかもしれませんよ。
山本:僕は自分のことでさえ分からなくなることがあります(笑)。それなのに教育現場では、教員が他人である子どもをあたかも理解しているように振る舞ってしまうことがよくありますよね。美化したり、レッテルを貼ったり……。
木村:これって傲慢だと思いませんか? 大空小学校では、校長や教員などの肩書きを外し、保護者や地域の方々も交えて、それぞれが1人の大人として子どもと接していました。若い教員がある子どものことを、さも分かったかのように「あの子はこうで、ああで……」と話している時にも、他の大人が「でもあの子は家ではこうなんだよね」とツッコむわけです。こうしたやり取りをしていると、教員も子どものことを分かったつもりになっている自分に気づく。そして子どもに対して「分からないから教えて」と素直に言えるようになるんです。