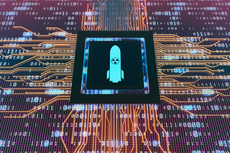ラテンアメリカでは異色、アルゼンチン・チリは欧州系白人社会
アルゼンチン・チリの有名観光地だけを駆け足で旅行する外国人は、両国における先住民の存在を、ほとんど意識することはないのではないだろうか。例えばペルー、ボリビアの著名な観光地であるマチュピチュ、クスコ、チチカカ湖、ウユニ塩湖、ポトシ銀山などを急ぎ足でまわる外国人旅行者は、歴史的な先住民の遺跡だけでなく、鮮やかな民族衣装を着た先住民(indigenas)や伝統的民芸品により否応なく先住民文化世界を体感する。それもそのはずで総人口に占める先住民の比率はペルーが50%、ボリビアが60%と高い。
ところが、アルゼンチン・チリ両国は圧倒的に欧州系白人世界である。人口4700万人のアルゼンチンでは、人口の半数超の2500万人がイタリア系といわれている。スペイン系など他の欧州系を合わせると、90%超が欧州系白人。先住民系は3%とごく僅か。人口2100万人のチリでも、スペイン系やドイツ系など欧州系が87%で先住民系は13%に過ぎない。
インカ帝国、スペイン人に抵抗したマプチェ族『大地に生きる人々』
アルゼンチン・チリ中南部地域に住んでいる先住民は、マプチェ族と呼ばれている。マプチェ族は南下して版図拡大を図るインカ帝国をくい止め、スペイン人征服者(conquitadores)に16世紀から300年以上も抵抗した誇り高い歴史を持つ。そしてスペインから独立したアルゼンチンにも抵抗した。
19世紀後半アルゼンチン政府は、近代的白人国家建設を目指した。欧州からの移民を積極的に受け入れ、パタゴニアなど政府の実行支配が及ばない未開拓地域の開発を進めて、産業革命がもたらした世界経済に対応しようとした。
障害となるパタゴニアの抵抗勢力、マプチェ族を掃討するために1870年代後半に大規模な軍事作戦を開始。最終的に1884年に族長が降伏して軍事作戦は終了した。これ以降マプチェ族の武力による組織的抵抗はなくなった。
同時期のチリでも同様の背景から陸軍が1861年からマプチェ族が多く住むアラウカニア地方制圧作戦を開始して1881年に族長が降伏している。
ブエノスアイレスからバリロ―チェまでの40時間、バスの車窓から
アルゼンチン国土はチリ同様に南北に長く3800キロメートルにもなる。北端の砂漠地帯からパタゴニア南端の氷の大地。そして中間地帯の広大で肥沃なパンパには農地・牧場が広がっている。ブエノスアイレス市街を出発して抜けて1時間ほどするとアルゼンチンの主要輸出品である牛肉を供給する牧場がパンパに広がっている。
ところがコロラド川を渡り、しばらくしてパタゴニア北部に入ると、荒れ地に灌木や茨が生えているような景観に変わってくる。そして不思議なことにバスが疾走する幹線道路の脇には、道路と並行して、木杭に有刺鉄線を張っただけの簡単な柵が、延々と設けられている。荒涼とした大地にも所有者がいるようだ。たまに羊の群れが見える。放牧されているのだろう。
バリロ―チェから1500キロメートル南下、パタゴニア南部の風景
アルゼンチンのエル・カラファテから、チリのプエルト・ナタレスに向かう途上のパタゴニア南部では、リャマのような動物をたびたび見かけた。ネットで調べたらグアナコというラクダ科の動物であった。リャマ、アルパカ、ビクーニャがアンデス山脈に生息しているのに対して、グアナコはパタゴニアが生息地らしい。 そして羊の放牧をたびたび見かけるようになった。エル・カラファテ~リオ・ガジェゴス~プエルト・ナタレスのルートのバスの停車場は〇〇アシエンダという地名が多かった。アシエンダは中南米では大農園を意味する。こうした大農園で羊の放牧をしているのだろうか。