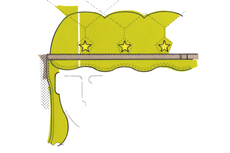第一次地方分権改革の成果は1999年の地方自治法改正、整備法による400本以上の法律改正という形で結実をみたところであり、若干の個別法では具体的な権限移譲も行われ、条例制定が可能となった。その代表例が都市計画領域であり、「分権の優等生」といわれる都市計画法は早い段階から地方の自主的な条例制定に途を開いてきた。
ところが、権限移譲後すでに10年余りが経過しているにもかかわらず、未だに「おっ」と目を引くようなレベルの高い条例は残念ながら見当たらない。
いわゆる「まちづくり条例」は全国津々浦々に存在しているが、その内容は金太郎飴さながら、行政指導ができる旨を定めるだけの法的には大して意味のないものばかりである。
これは全く遺憾なことで、条例は「法律の範囲内」で制定することができるのだから、法律が認めた権限を十二分に活用した条例が速やかに制定されて然るべきであるのに、分権以前の「要綱行政」と大差ない行政運営が漫然と行われ続けている。要綱というのは、行政職員が行政指導をするために用いる内部基準をいい、正式の規範である条例とは異なって法的拘束力を持たない。分権以前は自治体に法的権限がなく、条例制定が困難であったため、乱開発に悩む自治体の多くが宅地開発指導要綱や建築指導要綱などを作って、開発業者に対する行政指導を行ってきた。
しかし、行政指導はあくまでも相手方の任意を前提に行われるので、相手がこわもての悪質開発業者であるような場合はいかんともしがたく、ここに行政指導の限界がある。条例によって規制権限を明文化してはじめて、法的拘束力のある命令や禁止をすることが可能となる。
だが、実際問題として、自治体は規制権限があるにもかかわらず、「要綱上の行政指導」を「条例上の行政指導」にランクアップしただけで、有効な開発規制に踏み込むことができないでいる。
いち早く市町村に権限を付与した都市計画法では、その限界も他の分野に先駆けて明らかとなっており、06年の法改正では、開発規制について法律であらかじめ規制を設けることとし、条例による規制というスキームが一部返上された。これは地方の実力を踏まえた分権の揺り戻し現象に他ならない。
条例制定権拡大にリスクはないのか
国による一律基準に不合理な面があることは否定しないが、他方で、そうした基準が地方行政全体の最低レベルを保障する機能を果たしている点は、分権論議の中で看過されがちである。基準をはずせば、いい条例ができる可能性が開かれると同時に最低レベルを割るリスクが顕在化するのであり、地方の真の実力、等身大の地方行政が問われる。
地方分権論議において地方を善玉とする理想論が展開されるのはやむを得ないが、地方が想定どおりの有効な条例を制定できずにいる現実は、今後、住民にとって重い課題となろう。
自治体が有効な条例を制定できない原因としては、戦後ずっと行政指導に全面的に頼る行政スタイルできたために、条例に規制権限を定め、これを厳正に執行し、裁判で負けるかもしれないという訴訟リスクも辞さないという、法治国家であれば当然のやり方に全くなじんでいないことが背景にある。このことは、自治体職員の中に中央官庁に頼らずに自律的な法解釈、法制定をなしうる専門能力を備えた政策法務スタッフが揃っていないことや、自治体の顧問弁護士に行政法に精通した者が圧倒的に不足していることと無関係ではない。